!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/11/20
給与未払い・減額

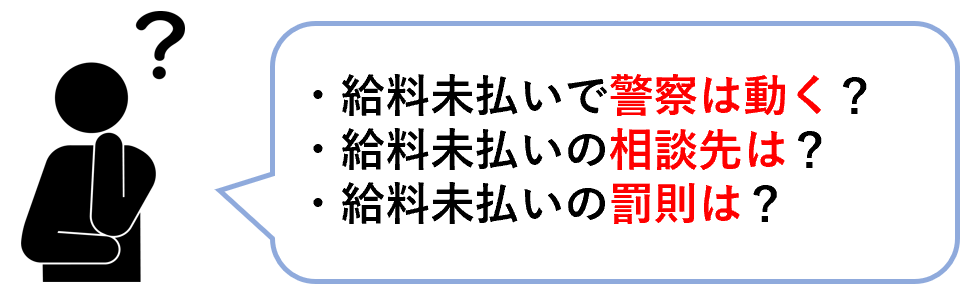
給料の未払いを警察に取り締まってほしいと悩んでいませんか?
働いたにもかかわらず給料が払わないというのは犯罪なのではないかと感じている方も多いですよね。
結論としては、給料未払いでは警察は動きません。
給料を支払ってほしいという弁護士、労働基準法違反の是正をしてほしいような場合には労働基準監督署に相談するといいでしょう。
もし、給料未払いに悩んでいる場合には、警察ではなく適切な相談先を選択したうえで、正しく対処していくようにしましょう。
ただし、給料未払いの相談をする際には、いくつかの注意していただきたいポイントがあります。
実は、給料未払いについては相談先が複数あり、あなたの意向や状況に応じて適切な相談先を選ばないと、十分に対応してもらえないことがあります。
この記事をとおして、給料未払いに悩んでいる方々に給料トラブルを解決するために知っておいていただきたいことをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、給料未払いでは警察は動かないことを説明したうえで、5つの相談先と簡単な正しい対処手順を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
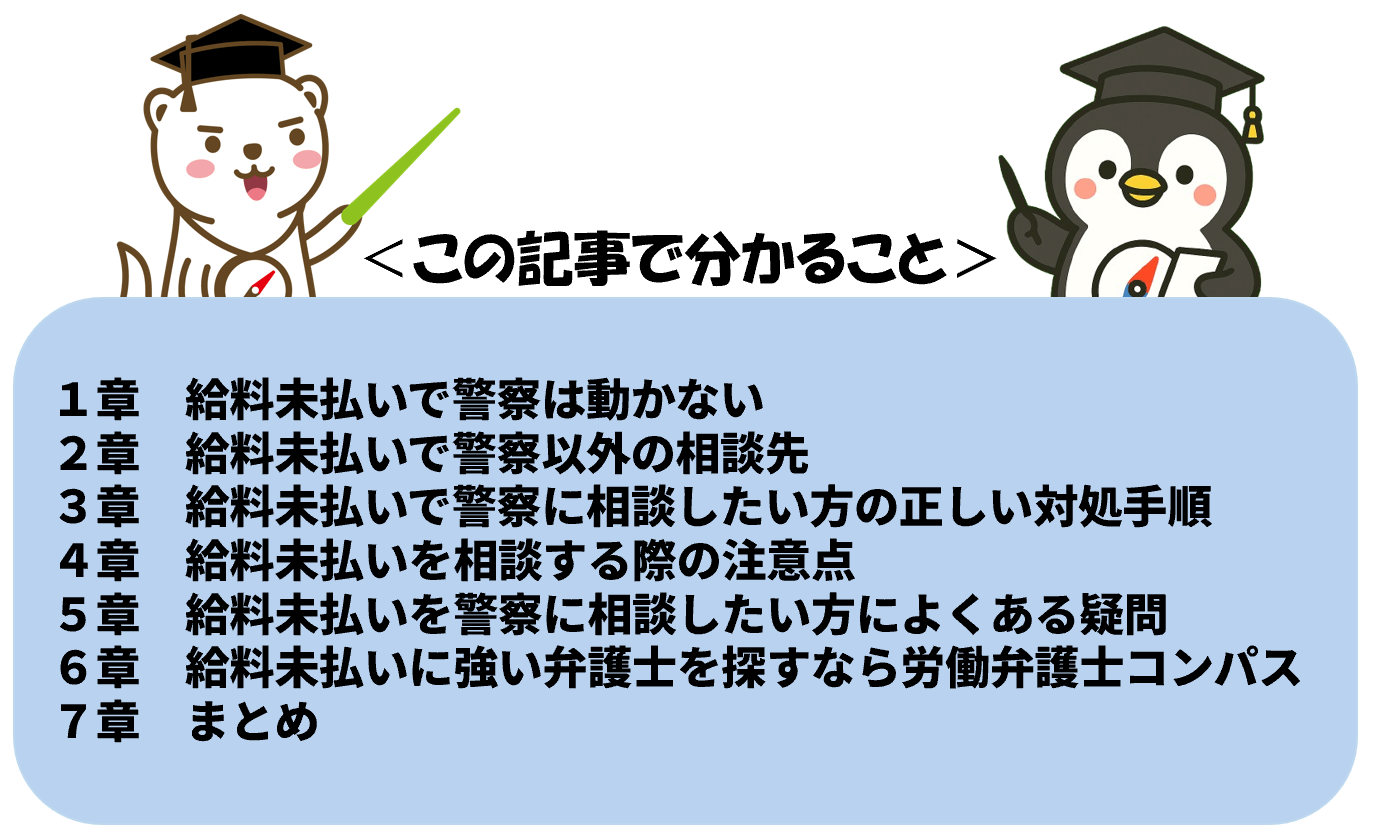
この記事を読めば、給料未払いについて警察ではなくどこに相談するべきなのかということがよくわかるはずです。
給料未払いで警察が動かないことについては、以下のショート動画で1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
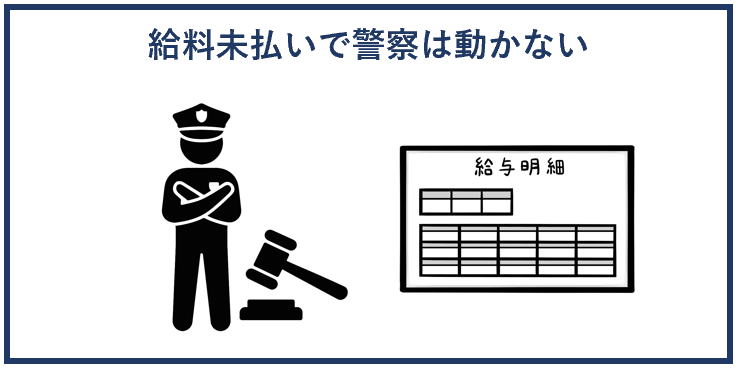
給料が支払われない場合でも、それだけで警察が動くことはありません。
なぜなら、給料未払いは民事上のトラブルとされるからです。
警察の仕事は、刑法などの法律に違反する「犯罪」を取り締まることです。暴行や窃盗などが代表的な刑事事件です。
労働基準法には刑事罰も課されていますが、労基法違反の刑事罰の管轄は警察ではなく、労働基準監督署になります。
例えば、ある労働者が「給料が支払われません」と交番に行っても、「それは民事の問題なので弁護士か労働基準監督署に相談してください」と案内されることが多いです。
警察が給料を代わりに取り立ててくれることはありません。
給料が支払われず困っている場合には、警察ではなく、弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することが大切です。
給料未払いを解決したいなら、警察ではなく他の専門機関に相談することが重要です。
なぜなら、給料未払いは民事上のトラブルとして扱われるため、警察が対応してくれないからです。
相談先を間違えてしまうと、対応を断られたり、解決が長引いたりするおそれがあります。
そのため、あなたの状況や目的に応じて、正しく相談先を選ぶことが大切です。
この章では、給料未払いで頼りになる相談先を紹介していきます。
具体的には、給料未払いで警察以外の相談先を5つ整理すると以下のとおりです。

それでは、それぞれの相談先について順番に見ていきましょう。
給料を取り戻したい場合には、弁護士に相談することがもっとも確実で安心です。弁護士は法律の専門家として、交渉から裁判まで一貫して対応してくれます。
なぜなら、弁護士は内容証明の送付や未払い給料の請求、さらには労働審判や訴訟といった法的手続きまで、すべてをサポートしてくれるからです。
会社にとっても、弁護士が対応することで無視しにくくなり、早期の支払いにつながる可能性があります。
例えば、弁護士が作成した内容証明を会社に送った結果、すぐに給料が支払われるというケースもあり得ます。会社が話し合いに応じない場合でも、法的手段に進むことが可能です。
費用はかかりますが、「より確実に給料を取り戻したい」「自分だけでは対応が難しい」と感じたときには、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
給料未払いを相談できる公的機関として、労働基準監督署があります。
労働基準法に違反していると判断されれば、会社に対して是正勧告などの指導が行われることがあります。
また、会社の対応が悪質な場合には、刑事事件として送検される可能性もあります。
例えば、労働基準法に違反した企業が、監督署の調査を受けたうえで送検され、罰金刑が科されるケースもあります。
ただし、労働基準監督署には給料を強制的に回収する権限はありません。対応に限界があることを理解したうえで、必要に応じて弁護士への相談も併用するとよいでしょう。
給料未払いに対して、労働組合に相談するという方法もあります。
労働組合は、労働者の立場から会社に対して団体交渉を行うことができるため、個人では言いづらい要求でもしっかり伝えてもらえる可能性があります。
交渉によって会社が未払い分を支払うことになったり、問題の再発防止を約束させたりするケースもあります。
労働組合には、企業内の組合だけでなく、どこに勤めていても加入できる「地域ユニオン」などもあります。
会社との直接のやりとりが不安な場合や、他の従業員と協力して対応したい場合には、労働組合に相談するのも有効な手段です。
給料未払いに関する相談を電話で手軽に行いたい場合は、「労働条件相談ほっとライン」を利用する方法があります。
厚生労働省が設けた窓口で、平日夜間や土日にも対応しているのが特徴です。
専門の相談員が、未払いの状況や相談者の立場に応じて、対応の流れや適切な窓口を案内してくれます。
匿名でも相談できるため、まずは話を聞いてみたいという方にも利用しやすい仕組みです。
直接的な解決はできませんが、どこに相談すべきか迷っている場合には、最初の相談窓口として活用するとよいでしょう。
給料未払いなどの労働トラブルについて、対面で相談したい場合は「総合労働相談コーナー」の利用がおすすめです。
都道府県ごとに設置されており、予約なしでも相談できるのが特徴です。
相談内容に応じて、労働基準監督署や労働局の担当部署と連携して対応してもらえることもあります。
状況を詳しく説明したうえで、最適な対応策を一緒に考えてもらえる点が大きなメリットです。
初めての相談でも丁寧に対応してもらえるので、どこに相談するか迷ったときの選択肢として活用できます。
総合労働相談コーナーの評判については、以下の記事で詳しく解説しています。
給料未払いで警察に相談したくなる気持ちは自然なことですが、実際には民事上の問題とされ、警察は対応してくれません。
そのため、法律にもとづいた正しい対処手順を知っておくことがとても大切です。
対応を間違えると、時間や労力だけがかかり、給料が回収できない結果になってしまうおそれがあります。
特に、証拠をそろえたり、適切な機関に相談したりする準備ができていないと、有効な手続きに進むことも難しくなります。
具体的には、給料未払いの場合には以下の手順で対処することがおすすめです。
それでは、給料未払いに対する正しい対処手順について見ていきましょう。
給料未払いが発生した場合、まずは弁護士などの専門機関に相談することが重要です。
法的な観点からアドバイスを受けることで、自分がどう行動すべきかが明確になります。
弁護士であれば、交渉や請求の代理はもちろん、労働審判や裁判に進む場合にも一貫してサポートを受けられます。法テラスを通じて無料相談が利用できることもあります。
労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉を行ってもらえることもあります。
例えば、「内容証明を送ったほうがよいのか」「労働審判を視野に入れるべきか」など、自分では判断しにくいことも、専門家の意見をもらうことで適切な対応がとれるようになります。
給料を回収が困難になる可能性がある場合や、会社とのやり取りに不安がある場合には、できるだけ早い段階で専門機関に相談するようにしましょう。
給料未払いを主張するためには、しっかりと証拠を集めておくことがとても大切です。
証拠がなければ、たとえ本当に働いていても、支払いを受けることが難しくなるおそれがあります。
具体的には、雇用契約書や給与明細、タイムカード、シフト表、LINEやメールでのやり取り、銀行口座の振込履歴などが証拠になります。
手元にある資料を見直し、未払いがあったことを客観的に示せるものを整理しておきましょう。
例えば、「〇月〇日に働いたのに給料が支払われていない」「支払日を過ぎても振り込まれていない」といった内容が記録されたメッセージや、出勤時間を記録したアプリのスクリーンショットも役に立つことがあります。
証拠が十分にそろっていれば、弁護士や労働基準監督署に相談する際もスムーズに話が進みます。少しでも手がかりになりそうな情報は、早めに保管しておきましょう。
証拠がそろったら、次は会社に対して未払い給料の支払いを正式に請求する段階に進みます。まずは口頭や書面での請求から始めるのが一般的です。
内容証明郵便を使えば、「いつ・いくらの給料が未払いであるか」「いつまでに支払ってほしいか」などを記録に残しながら通知できます。
会社に対してプレッシャーを与えやすく、交渉のきっかけにもなります。
例えば、「〇月分の給料〇万円が支払われていません。〇日までに支払われない場合は、法的手続きを検討します」といった文面を弁護士が作成し、内容証明で送付するケースもあります。
会社が支払いに応じればここで問題は解決します。応じない場合には、次のステップに進むことになります。
会社が任意に支払いに応じない場合には、労働審判や訴訟といった法的手段に進むことを検討します。これにより、強制的に支払いを命じる判断を求めることができます。
労働審判は、裁判所が間に入って短期間での解決を目指す手続で、話し合いによる解決が基本ですが、最終的には審判(判断)が出されることもあります。
労働審判では3回以内の期日で判断が下されることが多く、迅速に結果が出やすいとされています。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。解決までに1年以上を要することもあります。
費用や時間、労力もかかりますが、会社側が一切応じない場合には、これらの法的手段を検討することが現実的な選択肢となります。
給与未払いの裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。
給料未払いに直面したときは、早めに相談することが大切ですが、いくつか注意しておくべき点もあります。
誤った期待や手続きのミスがあると、相談しても思ったように進まないことがあるためです。
適切な窓口を選ばないと対応してもらえなかったり、強制力がないまま放置されたりすることもあります。
事前に正しい知識を持つことで、無駄な時間や手間を防ぎ、スムーズに解決へ向かうことができます。
例えば、給料未払いを相談する際には、以下の3つの点に注意するようにしましょう。
それでは、順番に見ていきましょう。
労働基準監督署は、給料未払いに対して行政指導を行うことができますが、会社に給料の支払いを強制する権限はありません。
つまり、命令に従わなかったとしても、すぐにお金を取り戻せるわけではないのです。
監督署ができるのは、あくまで是正勧告や調査などの対応であり、あなたに代わって会社の財産を差し押さえてくれるわけではありません。
悪質なケースでは送検されることもありますが、それでも実際に給料を回収するには、別途、労働審判や訴訟などの法的手続きが必要になります。
例えば、監督署に相談しても会社が指導に従わず、結局は弁護士を通じて内容証明や裁判を行わざるを得ないケースもあります。
労働基準監督署に相談することは第一歩として有効ですが、それだけで解決できるとは限らないため、他の手段と併用することも考えておくと安心です。
給料未払いの相談は、内容や目的に応じて正しい窓口を選ぶことが大切です。
相談先を間違えてしまうと、「ここでは対応できません」と言われてしまい、解決が遠のくおそれがあります。
例えば、実際に給料を回収したいなら弁護士、労働基準法違反の是正を求めたいなら労働基準監督署、働き方全般の助言がほしいなら総合労働相談コーナーなど、それぞれ役割が異なります。
相談したのに具体的な対応が何も進まなかったという場合、その原因は「相談先が目的に合っていなかった」ということも多いのです。
事前に自分の希望や状況を整理し、目的に合った機関を選ぶことで、より効果的な対応につながります。
給料未払いに気づいたら、できるだけ早く相談することがとても重要です。
対応が遅れるほど、証拠がなくなったり、時効が進行したりして、回収が難しくなる可能性があります。
未払い給料の請求には原則として3年の時効があります。その期間を過ぎてしまうと、正当な請求でも認められないおそれがあります。
例えば、「忙しいから後回しにしていたら、時効を過ぎて請求できなくなった」というケースもあります。相談が早ければ、証拠の確保や手続きの選択肢も広がります。
不安を抱えたまま時間だけが過ぎる前に、まずは一度、専門機関に相談してみることをおすすめします。
給料未払いを警察に相談したい方によくある疑問としては以下の3つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A:給料未払いに対しては、条件を満たせば刑事罰が科される可能性もあります。
すべての未払いが刑事事件になるわけではありませんが、悪質なケースでは会社が処罰されることもあります。
労働基準法では賃金の支払いに関する規定である労働基準法24条に違反した場合には、30万円以下の罰金に処すると規定されているためです(労働基準法120条)
A:アルバイトでも、正社員と同じように給料未払いを請求することができます。
労働基準法では、アルバイトやパートといった非正規労働者であっても、「労働者」としての権利が認められているためです。
アルバイトだからといって泣き寝入りする必要はありません。未払いがある場合には、証拠をそろえたうえで、正規雇用と同じように適切な対応を取りましょう。
A:キャバクラやバーなど、いわゆる夜職であっても、雇用契約や実際の労働実態があれば、働いた分の給料は請求できます。
労働基準法では、業種や時間帯にかかわらず、使用者が労働者に賃金を支払う義務を負っています。
給料未払いに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、給料未払いでは警察は動かないことを説明したうえで、5つの相談先と簡単な正しい対処手順を解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が給料の未払いを警察に取り締まってほしいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。