!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/08/21
労働災害
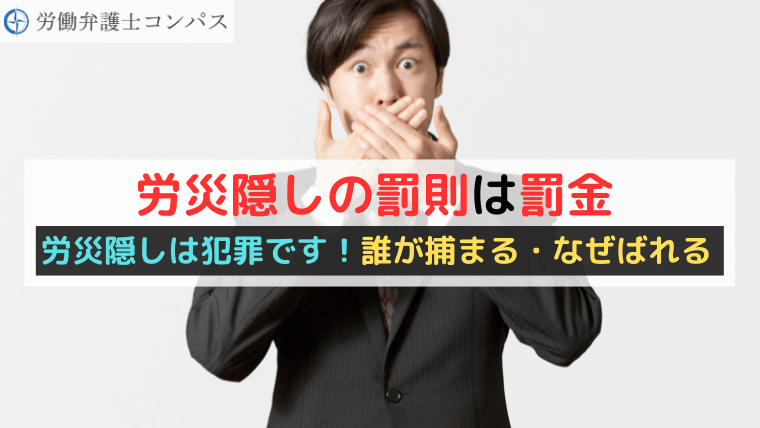
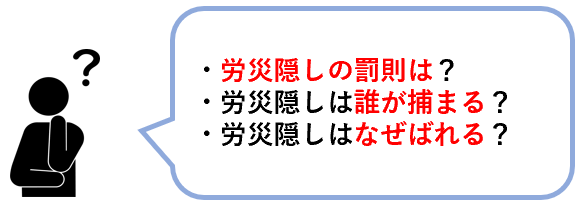
労災隠しをされてしまい罰則を科すことができないか知りたいと悩んでいませんか?
会社のせいで負傷したり、病気になったりした場合に、真摯に対応してもらうことができなければ不満に感じるのは当然のことですよね。
労災隠しをした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
労災隠しは刑罰が定められている犯罪の1つなのです。
労災隠しについては、これを行った会社だけではなく、労災隠しに関与した方も処罰の対象となります。
労災隠しは、労働者本人からの通報で発覚することが多いですが、医療機関や第三者からの通報で発覚することもあります。
労災隠しの罰則の公訴時効は3年です。
もし、労災隠しをされた場合には、あなた自身の権利を守るためにも適切な対処をしていく必要があります。
実は、会社は、労災の認定がされた場合、損害賠償請求や労災保険料が上がるリスクがあるため、労災の申請に非協力的であることも珍しくないのです。
今回は、労災隠しの罰則について労災隠しは犯罪であることを説明したうえで、誰が捕まるか、なぜばれるのかなどを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
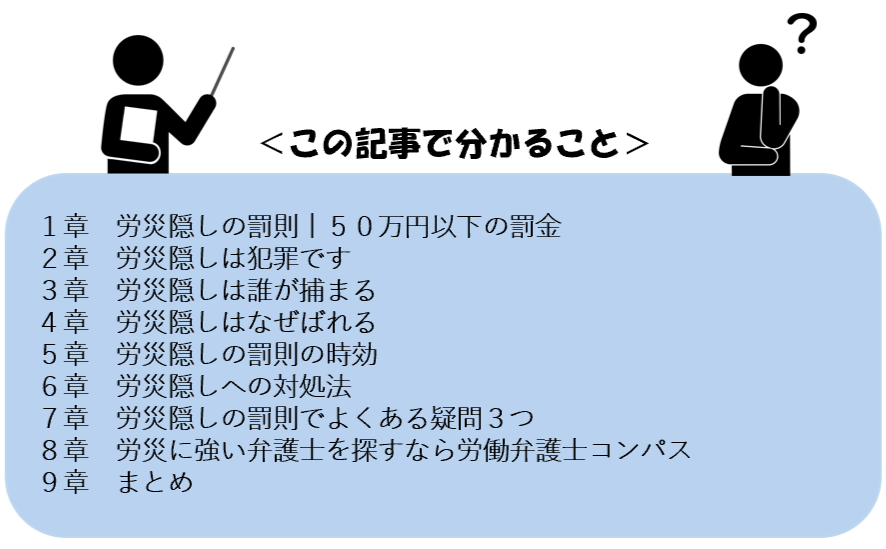
この記事を読めば、労災隠しが犯罪であり行ってはいけないこと、及び、その罰則についてよくわかるはずです。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
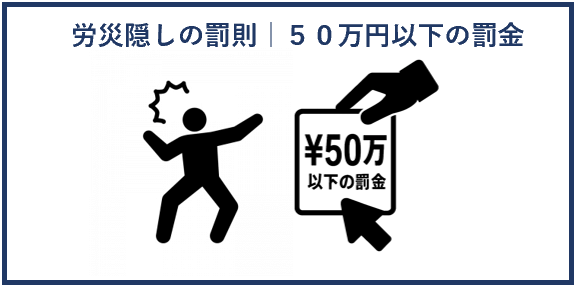
労災隠しをした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則では、以下のとおり定められているためです。
つまり、労働者が仕事中に負った怪我などついて、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合には、50万円の罰則が科されるとの内容になっています。
例えば、製造業の現場で、作業員が機械に手を挟まれ負傷したとします。本来であれば、会社はすみやかに労働基準監督署へ報告し、労災保険の手続きを取る必要があります。
ところが、会社が「会社の評価に響く」「労災件数を増やしたくない」という理由で報告をせず、「私的なケガだったことにしよう」と指示した場合、これは明確な労災隠しです。
こうしたケースでは、労働安全衛生法違反として、会社や担当者に罰金が科される可能性があります。

労災隠しは、単なる社内ルール違反やモラルの問題ではなく、法的に「犯罪」として明確に位置づけられています。
労働者の安全や健康にかかわる情報を意図的に隠したり、事実を偽って報告したりする行為は、社会的にも非常に悪質なものとされています。
本来、会社には労働者の命と健康を守る義務があります。労災が起きた場合、その事実を正確に報告することは、企業として当然の責任です。それを隠すということは、労働者の保護をないがしろにし、制度そのものを機能不全に陥らせる行為にほかなりません。
また、労災を隠すことで、労働者が本来受け取るべき治療費や休業補償、後遺障害への給付などが正当に支払われなくなる恐れがあります。これは労働者の生活を直接的に脅かす重大な問題です。
さらに、労災隠しがまかり通る職場では、同様の事故が繰り返される危険もあります。再発防止策が取られず、安全意識の欠如した環境が固定化してしまうのです。
このように、労災隠しは、企業としての信頼を失うばかりか、社会的にも非難されるべき行為です。結果として、企業自身にとっても大きなリスクを生むことになります。
だからこそ、労災隠しは法律により「犯罪」とされ、刑事罰の対象とされているのです。
労災隠しについては、雇用主である法人と労災隠しに関与した方の両方が処罰の対象となります。
実際に誰が責任を問われるのかについては、関与の程度や立場に応じて異なります。
例えば、労災隠しの刑事罰の対象としては以下のとおりです。
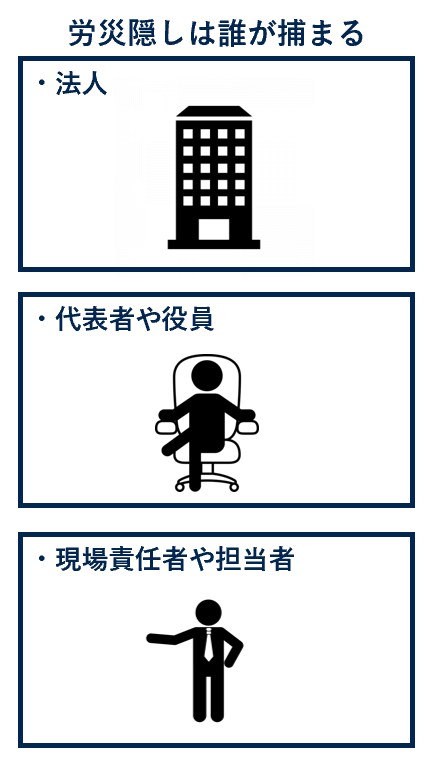
労災隠しがあった場合には、雇用主となる法人が刑事罰の対象となる可能性があります。
法人の従業員が労災隠しを行った場合には、その行為者だけではなく、法人に対しても、罰金刑が科されるとされているためです。
労災隠しがあった場合には、代表者や経営者も刑事罰の対象となる可能性があります。
処罰の中心となるのは、労災の報告義務を負っていた「事業者」または「使用者」、つまり代表者や経営者だからです。
例えば、代表者や経営者が労災の発生を知りながら報告を指示しなかった場合、その人自身が罰せられる可能性があります。
労災隠しがあった場合には、現場責任者や担当者も刑事罰の対象となる可能性があります。
例えば、報告書の改ざんを行ったり、従業員に「通勤中のケガだったことにしてほしい」などと指示したりした場合も、その行為者本人が処罰されるケースもあります。
労災隠しに積極的に加担したわけではなくても、上司からの指示に従い、形式的に書類の提出だけを行ったような場合でも、事情によっては責任を問われることがありますので注意しましょう。
つまり、労災隠しの責任は組織全体に及ぶ可能性があり、「上から言われたからやった」では済まされない重大な問題です。
会社が労災隠しをしたとしても、簡単に発覚します。
労災は、仕事中や通勤中の怪我や病気であり、医療機関での診療や、関係者の証言、現場の記録など多くの痕跡が残るためです。
そのため、どんなに隠そうとしても、ある日突然明るみに出ることが少なくありません。
例えば、労災隠しは、以下のようなルートで発覚することがよくあります。
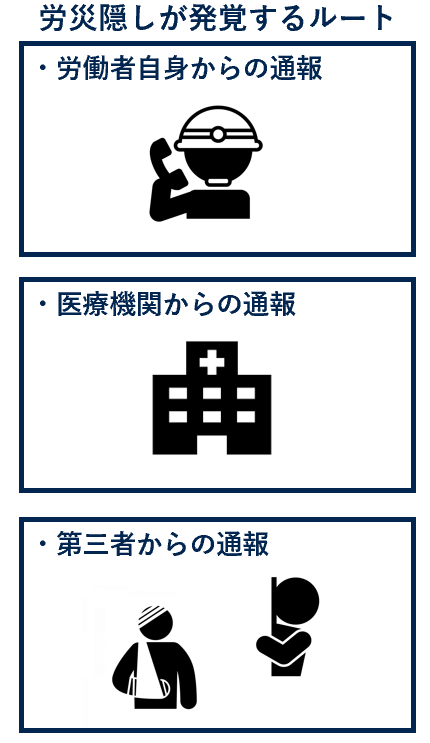
それでは、労災が発覚する状況について順番に説明していきます。
もっとも多いのが、被害を受けた労働者本人が、会社の対応に不信を抱き、自ら労働基準監督署へ通報するケースです。
最近では、インターネットやSNSで簡単に情報収集することが可能になったため、会社の圧力を受けても、自ら行動を起こす人が増えてきています。
例えば、「通勤中にケガをしたのに健康保険で処理された」「業務中に大けがをしたのに、労災申請をするなと言われた」といった状況では、労働者自身が労基署に相談することが多くあります。
こうした通報がきっかけで、監督署が調査に乗り出し、隠されていた事実が明るみに出るのです。
労災隠しの告発については、以下の記事で詳しく解説しています。
もう一つの代表的な経路が、病院や診療所といった医療機関からの通報です。
医療機関は、労災保険適用の可否について敏感であり、業務起因性があると診断すれば、当然労災手続を勧める立場にあるためです。
ここで不自然な対応があれば、通報に発展する可能性は十分あります。
例えば、労働者が「業務中にケガをした」と申告しているのに、会社側が健康保険での診療を求めてきた場合、医師や事務方が不審に思い、労働基準監督署に連絡することがあります。
労災の医療費については、以下の記事で詳しく解説しています。
意外と見落とされがちですが、労働者本人や医療機関以外の第三者からの通報も珍しくありません。
会社内での事故については同僚などの目撃者がいますし、SNSでの発言などがきっかけとなって外部の目に触れ、通報へと発展することもあります。
同僚や元従業員、家族、さらには取引先の人などが、労働者のケガや体調悪化の経緯を聞き、「これはおかしい」と感じて労働基準監督署へ通報するケースもあります。
労災隠しに対する罰則にも「時効」があります。
公訴時効という制度が適用され、刑事責任を問える期間に制限があるためです。
具体的には、労災隠しの罰則の公訴時効は、3年です。
つまり、労災隠しが行われた日から3年が経過してしまうと、たとえ事実が発覚しても、原則として刑事罰を科すことはできなくなります。
例えば、ある会社が2022年5月に起きた労災を隠していた場合、2025年5月までに公訴が提起されなければ、その件については罰金などの刑事処分を科すことはできなくなってしまう可能性があるということになります。
ただし、公訴時効が完成した場合であっても、民事上の損害賠償請求の消滅時効は完成していない場合があります。
そのため、労災隠しをされたと感じた場合は、できるだけ早期に相談や対応を行うことが重要です。
会社側が時効を狙って「時間が経てばうやむやになる」と考えていることもありますので、逃げ得を許さないようにしましょう。
労災申請の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
もし、労災隠しをされた場合には、あなた自身の権利を守るためにも適切な対処をしていく必要があります。
会社側が労災を隠そうとしている以上、あなた自身が行動を起こさなければ、労災はなかったものと扱われてしまうリスクがあるためです。
具体的には、労災隠しをされた場合には、以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
労災隠しへの対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
法的な見通しや手続について助言をしてもらうといいでしょう。
また、労災において適切な補償を受けるためには、ポイントを押さえたうえで、あなたに有利な事実を説得的に説明していくことが大切です。弁護士のサポートを受けながら手続きを進めるといいでしょう。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、労災に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
労災隠しへの対処法の2つ目は、提出書面や資料の準備です。
労災の申請をするためには、厚生労働省のホームページなどで請求書をダウンロードして必要事項を記入する必要があります。
また、事業主や医師の証明を記載する欄などがありますので、協力を求めることになります。
事業主に協力してもらえない場合には、その経緯等を労基署に説明することになります。
その他、あなたに有利な事情については、別紙にまとめたり、資料を添付したりして提出することになります。
労災隠しへの対処法の3つ目は、労基署に提出することです。
管轄の労基署を調べたうえで、申請書等を一式提出することになります。
事前に労基署に電話してアポイントを取っておくとスムーズです。
労災隠しへの対処法の4つ目は、労基署の調査に協力することです。
労基署は労災の申請があったら、労災の認定をすることができるか調査を行うことになります。
会社に資料の提出を求めたり、関係者にヒアリングをしたり、専門家の意見を仰いだりします。
労働者自身にもヒアリングに協力するようお願いされることがありますので、必要に応じて手続きに協力することになります。
労災隠しの罰則でよくある疑問としては、以下の3つがあります。
これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A.いいえ、労災隠しの通報先は基本的に労働基準監督署です。
警察に通報しても、労働法に基づく取り締まり権限はないため、対応できません。
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて、企業の労働環境を監視・指導する役割を担っています。
労災の隠蔽や虚偽の報告が疑われる場合は、最寄りの労基署に相談・通報してください。
匿名での通報も可能なので、不安がある場合でも安心して相談できます。
A.会社が労災を隠そうとする背景には、以下のような理由があります。
しかし、こうした自己都合による隠蔽は法律に反するだけでなく、後々に発覚した場合には企業イメージや信頼性を大きく損なうことになります。
A.罰則が科されることと、労働者が補償を受けられるかどうかは、原則として別の問題です。
労災保険による補償を受けるためには、労災の申請を行う必要があります。
会社が労災を認めなくても、労働者自身で労災の申請を行うことは可能ですので、自分で行動を起こすようにしましょう。
労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、労災隠しの罰則について労災隠しは犯罪であることを説明したうえで、誰が捕まるか、なぜばれるのかなどを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
労災隠しをされてしまい罰則を科すことができないか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。