!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/12/10
不当解雇

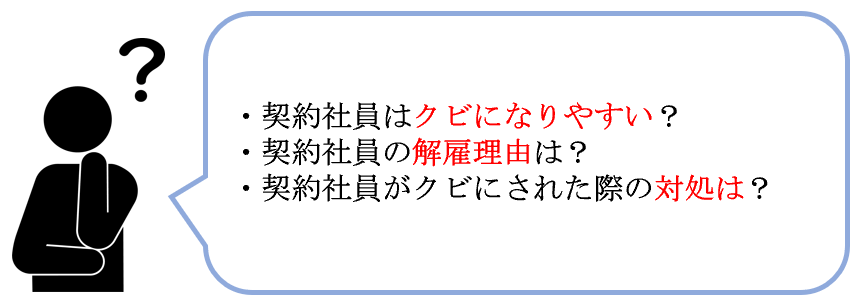
契約社員として働いているものの解雇されてしまい困っていませんか?
契約社員の地位が不安定であるという話を聞いたことがある方もいるでしょうが、いざクビにされてしまうとこれからの生活が心配ですよね。
契約社員は、期間中はクビになることは少ないですが、期間満了時に契約の更新を拒絶されてしまうことによりクビとなることが多くなっています。
契約社員は、契約期間中について、解雇できないというわけではありませんが、正社員以上に強く保護されています。
契約社員がクビになる理由として多いのは、期間満了や能力不足ですが、業務態度を理由とされることもあります。
契約社員の更新拒絶であっても、更新の期待が認められる場合には、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と言えなければ、不当となります。
契約社員をクビにする場合には、期間中の解雇、及び、期間満了時の更新拒絶のいずれについても、30日前の予告が必要とされることがあります。
契約社員がクビになった際には、これからの生活を守るためにも、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。
実は、契約社員だからといって必ずしもクビにすることが許されるわけではありませんが、会社の言い分を鵜吞みにしてしまい、あきらめてしまっている労働者の方がたくさんいます。
この記事をとおして、契約社員として働く多くの方に解雇についての考え方をわかりやすく説明することができれば幸いです。
今回は、契約社員はクビになりやすいかを説明したうえで、期間満了や能力不足の解雇と対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
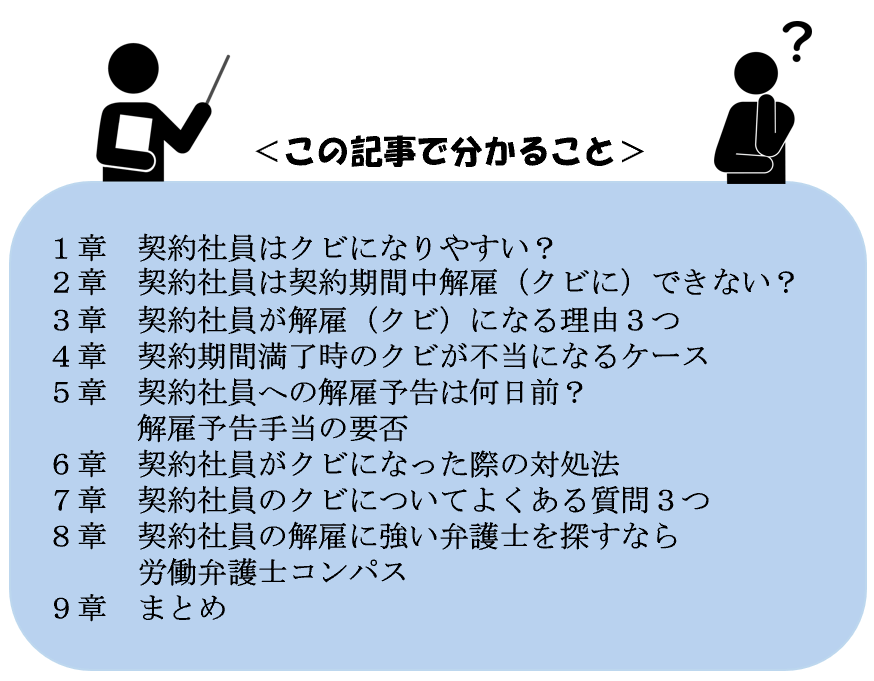
この記事を読めば、契約社員として働く方がクビになった際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

契約社員は、期間満了時に契約の更新を拒絶されてしまうことにより、クビとなることが多くなっています。
なぜなら、契約社員は、契約期間が定められていて、あくまでもその期間の範囲で雇われているにすぎないためです。
契約期間が満了すれば、契約が更新されない限りは、雇用契約も終了することになります。
例えば、2025年4月1日に6か月の契約期間で雇用された方の場合には、2025年9月末日をもって契約期間が満了し、更新がされなければ雇用契約は終了となります。
契約期間満了における更新拒絶は、契約終了により労働者が退職することになるものであり、会社側が一方的な通知で労働者を退職させる解雇とは区別されています。
そのため、契約期間満了による更新拒絶には、解雇権濫用法理は適用されず、原則として、会社側が更新を拒絶したとしても、違法とはなりません。
そこで、会社側は、人件費を削減しようとする際には、正社員を解雇するのではなく、まずは契約社員の更新を拒絶することを優先するのです。
できない?.png)
契約社員は、契約期間中について、解雇できないというわけではありませんが、正社員以上に強く保護されています。
契約期間を決めて採用した以上、少なくともその期間中は雇用をし続けることが前提とされているためです。
法律上、契約期間中については、やむを得ない事由と言う例外的な事情がなければ、解雇することはできないとされています。
つまり、契約社員については、契約期間中については、正社員以上に強く保護されているのです。
例えば、2025年4月1日に6か月の契約期間で雇用された方が、2025年6月末日で解雇された場合には、契約期間は3か月残っており契約期間の解雇となります。
そのため、例外的にやむを得ない事由があったということができなければ、解雇は不当なるのです。
契約社員がクビになる際には理由があります。
クビになる理由を知ることで、不利になってしまわないように対策も講じやすくなります。
例えば、契約社員がクビになる理由としては、以下の3つがあります。
になる理由3つ.png)
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
契約社員がクビになる理由の1つ目は、期間満了です。
これまでにも説明したとおり、契約期間満了をもって、更新を拒絶しないとして、退職になってしまうことがあります。
会社側が更新を拒絶しない理由は様々ですが、会社の業績や繁忙状況、労働者の成績や態度、心身の状況などが加味されます。
契約社員がクビになる理由の2つ目は、能力不足です。
能力が不足していて会社に重大な損害を与えてしまう場合や改善の見込みがないような場合には、クビにされてしまうことがあります。
例えば、能力が不足していることを理由として、契約の更新を拒絶されてしまうことがあります。
契約期間中であっても、あなたのパフォーマンスは期待に達していないので、期間満了まで、もう出勤しなくて構わないなどと言われることもあります
能力不足を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約社員がクビになる理由の3つ目は、業務態度です。
上司や同僚への不適切な態度や指示の無視、遅刻や欠勤の多さ、業務中の私用行為などは、信頼を損なう行為と見られてしまうためです。
例えば、職場での協調性が欠けている、報告や連絡を怠る、または業務中に集中力を欠いている行動を取ると、職場全体の士気や生産性に悪影響を与えます。
契約社員として信頼を得るためには、真摯な姿勢で業務に取り組み、職場での良好な関係を築くことが不可欠です。
業務態度を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約社員の更新拒絶であっても、更新の期待が認められる場合には、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と言えなければ、不当となります。
労働契約法という法律で、雇い止め法理が規定されているためです。
更新の期待があるかについては、更新の回数や通算期間、更新の手続、業務内容、会社側の採用時や更新時の言動などが考慮されることになります。
例えば、何度も更新されていて、長期にわたり働いてきた方で、契約の更新も自動で行われており、長く勤務してほしいなどと言われている場合には、更新の期待が認められる可能性が高いでしょう。
更新の期待が認められた場合には、更新を拒絶するには客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることが必要となります。
更新拒絶の理由が事実なのか、事実として雇用を継続できないほど重大なものか、更新を拒絶せずに済むように他の措置を検討したかなどが検討されることになります。
更新の期待が認められ、更新の拒絶が客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でない場合には、更新の申し込みは承諾されたものとみなされることになります。
契約社員をクビにする場合には、期間中の解雇、及び、期間満了時の更新拒絶のいずれについても、30日前の予告が必要とされることがあります。
まず、会社が、契約社員を契約期間中に解雇する場合には、正社員と同様、原則として、30日前に解雇予告を行う必要があります。
ただし、不足する日数に相当する解雇予告手当を支給することで、予告期間を短縮することができます。
次に、契約期間満了時の更新拒絶も、以下のいずれかに該当する場合には、30日前に予告することが必要とされています。
ただし、この場合でも、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されているケースでは、更新拒絶の予告は不要とされています。
解雇予告手当をもらえない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約社員がクビになった際には、これからの生活を守るためにも、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。
適切に対処していくことで、あなたの権利を守ることができることも多いのです。
具体的には、契約社員がクビになった際には、以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
契約社員がクビになった際の対処手順1つ目は、弁護士に相談することです。
弁護士に相談することで法的な見通しが明らかになりますし、あなたが不利にならないようにするためにはどのように対応していけばいいのか助言してもらうことができます。
契約社員がクビを争う際には、早い段階で、有利な証拠を集めていくことが大切です。
ただし、契約社員のクビについては専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題に力を入れていて、契約社員のクビの問題に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
契約社員がクビになった際の対処手順2つ目は、通知書を送付することです。
更新拒絶をされたのか、解雇をされたのかによって、通知する内容も変わってきますが。
いずれにせよ、クビにすることが認められないことが指摘したうえで、まだ社員としての地位にあることを主張していくことになります。
また、更新拒絶や解雇を争うにあたっては、会社側にクビにした理由を明らかにするよう求めていくことになります。
労働者としても、どのような主張や証拠を準備すればいいのかを把握することができますし、見通しもより明確になるためです。
契約社員がクビになった際の対処手順3つ目は、交渉することです。
裁判を用いた解決については労力も時間も必要となるため、まずは話し合いにより解決することができないか協議しましょう。
双方の言い分を踏まえて争点についての見通しを分析したうえで、折り合いをつけることが可能かどうか議論し、落としどころを決めることになります。
示談により解決することができれば、早期に少ない負担で良い解決をすることができる可能性があります。
契約社員がクビになった際の対処手順4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
まずは、労働審判を用いた解決を検討してみるのがおすすめです。
労働審判とは、全3回の期日で調停による解決を目指す手続きです。裁判所を入れた話し合いのようなイメージです。
裁判所の心証を踏まえて話し合いが行われるため、裁判外の交渉に比べて、法的な見通しに基づいた解決を行いやすくなっております。
調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下すことになり、労働者又は会社のいずれかが異議を出した場合には、通常の訴訟に移行することになります。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。
訴訟については、期日の回数の制限などはとくにありません。裁判所の指揮に応じて、1か月に1回程度の頻度で、労働者と会社が交互に主張を繰り返していくことになります。
解決まで1年以上を要することもあります。
不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
不当解雇の訴訟については、以下の動画でも詳しく解説しています。
契約社員のクビについてよくある質問として以下の3つがあります。
それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A.契約社員は、契約期間が通算5年を超える前にクビにされてしまうことが多くなっています。
5年を超えると労働者の一方的な要求で無期労働契約への転換をすることができるためです。
いわゆる無期転換ルールと言われるものです。
会社側は、労働者から無期転換権を行使される前に、更新を拒絶したり、解雇したりして、無期転換権の行使を防ごうとすることがあるのです。
A.契約社員のクビについては、その理由により、失業保険上の処理も異なってきます。
まず、契約期間中の解雇については、原則として、会社都合となります。離職票上、「解雇(重責解雇を除く。)」にチェックされることになるためです。
ただし、刑法の規定違反や重大な就業規則違反等による解雇の場合には、「重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)」として、自己都合になります。
会社都合とされると、失業保険の受給条件や給付までの期間、給付日数について、自己都合よりも有利に取り扱ってもらうことができます。
次に、契約期間満了に伴う更新拒絶については、以下の場合には、会社都合退職となります。
また、「期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新または延長があることは明示されているが更新または延長することの確約まではない場合」は、会社都合ではありませんが、特定理由離職者として会社都合と同様、有利に扱ってもらえます。
クビになった場合の失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.契約社員は、いきなりクビにされてしまうこともあります。
期間中の解雇や更新拒絶の予告には例外もあるためです。
例えば、期間中の解雇については、解雇予告手当を払えば予告を短縮できますので、解雇予告手当を支払って即日解雇されるようなこともあります。
また、更新拒絶については、更新回数が3回未満で、かつ、契約期間が1年未満の場合には、予告は不要とされています。
更新しないことがあらかじめ明確にされている場合には、更新の拒絶は不要とされています。
ただし、いきなりクビにすることはトラブルになることが多いため、会社は契約社員をクビにする前に退職届や合意書などにサインを求めてくることもあります。
解雇の前兆については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約社員の解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、契約社員はクビになりやすいかを説明したうえで、期間満了や能力不足の解雇と対処法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が契約社員として働いているものの解雇されてしまい困っている労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。