
2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。
2025/11/25
法律相談

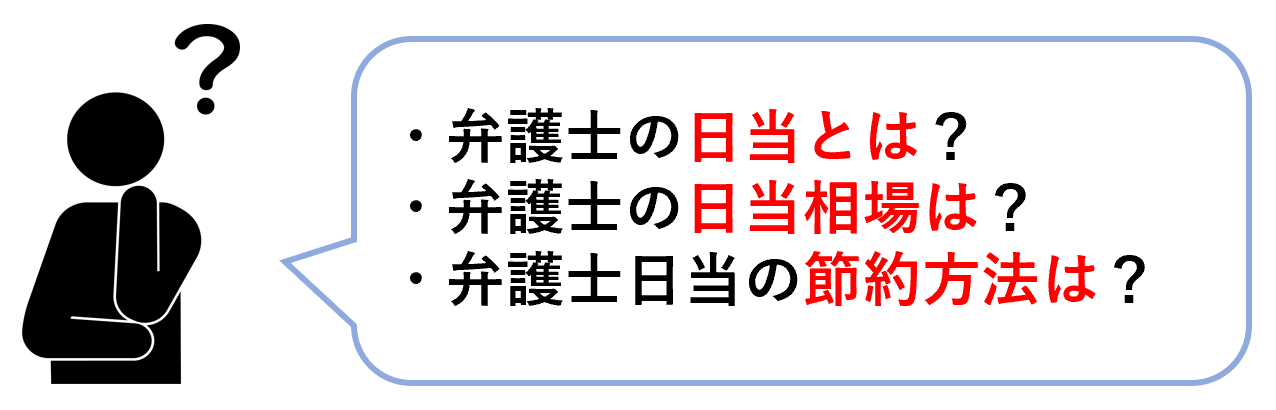
弁護士の日当について知りたいと悩んでいませんか?
着手金や報酬金と違って、どの程度の金額になるか分かりにくいので、不安に感じてしまう方もいますよね。
弁護士の日当とは、裁判の期日などで弁護士の時間が拘束されたことへの対価として支払われる費用です。
出張日当の相場は3万~10万円程度、出廷日当(出頭日当)の相場は2万円~5万円程度です。
弁護士の日当については、工夫することで節約することができます。
また、弁護士に依頼する際には日当以外にもかかる費用がありますので、これについても抑えておくようにしましょう。
実は、弁護士の日当は時間や負担に応じて金額を調整できる点で合理性がある一方で、遠方であったり長期化したりすると高額化しやすいため注意も必要です。
この記事をとおして、弁護士の日当で損をしないために知っておいていただきたいことを誰でも分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、弁護士の日当とは何かを説明したうえで、相場や出張・出廷日当と消費税や節約方法3つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
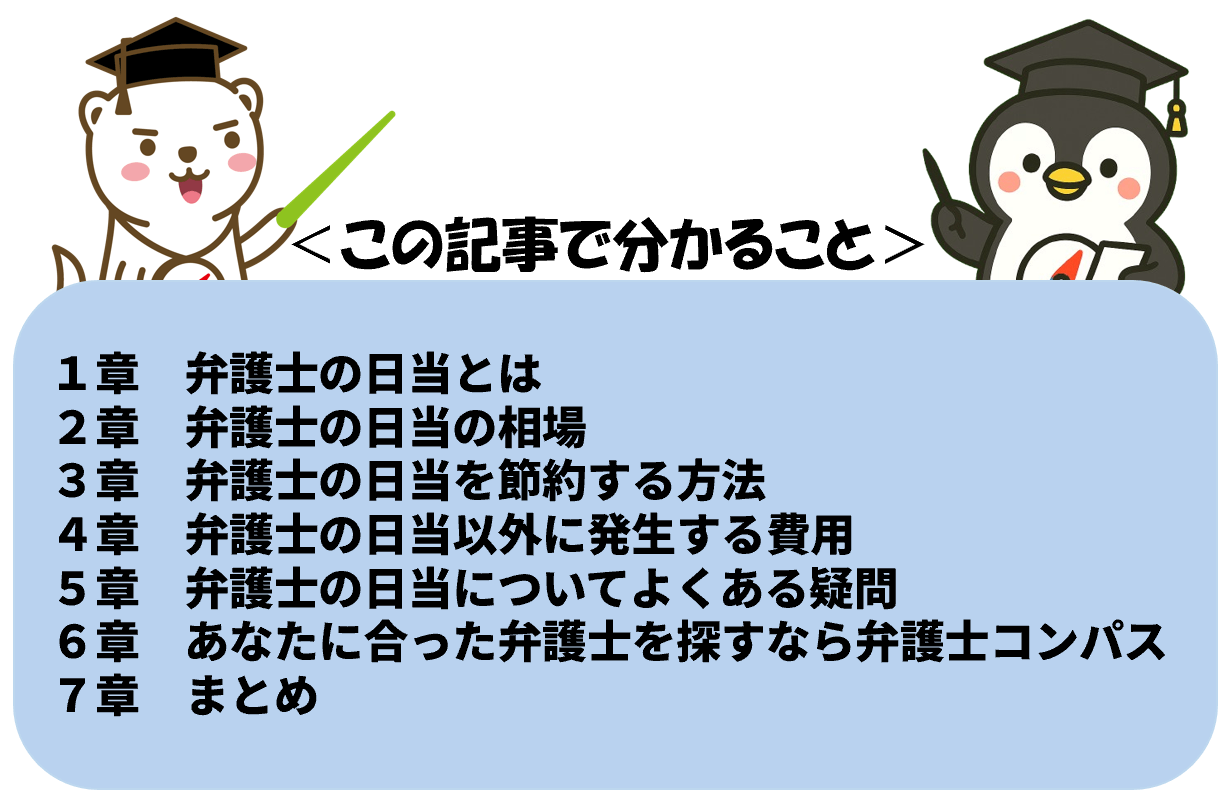
この記事を読めば、弁護士の日当で後悔しないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す
弁護士の日当とは、裁判の期日などで弁護士が時間的に拘束されたことへの対価として支払う費用です。
これは依頼者にとっても大きな負担となることもあるので、仕組みを理解しておくことが大切です。
例えば、弁護士の日当には以下のような種類があります。
それでは、弁護士の日当の具体的な種類について順番に見ていきましょう。
出張日当とは、弁護士が裁判所や相手方との交渉のために遠方へ移動する場合に発生する費用です。
これは単に交通費だけでなく、長時間の移動や宿泊を伴うことによる負担に対する対価でもあります。
例えば、地方の裁判所で期日がある場合や、尋問のために現地へ出向く場合に出張日当が請求されるケースがあります。
このように、出張日当は「移動や宿泊を伴う負担」に応じて設定される費用だと理解しておきましょう。
出廷日当(出頭日当)とは、弁護士が裁判期日に出廷する場合にかかる費用です。
これは移動距離に関係なく、裁判に出席するために弁護士の時間が拘束されることへの対価です。
期日自体の拘束時間としての意味というよりも、期日の回数を基準に弁護士の負担に応じて費用調整するために、出廷日当という形式がとられていることもあります。
例えば、解決までにかかった期日の回数が6回であれば、2万円×6期日=12万円を日当として請求されると言った方式となります。
このように、出廷日当(出頭日当)とは、期日の回数に応じて支払うことになる費用と理解しておきましょう。
弁護士の日当の相場は、出張か出廷かによって異なります。
通常、委任契約書に日当の金額が記載されています。
出張日当の相場はおおむね3万円から10万円程度とされています。
一方、出廷日当(出頭日当)の相場は、2万円から5万円程度です。
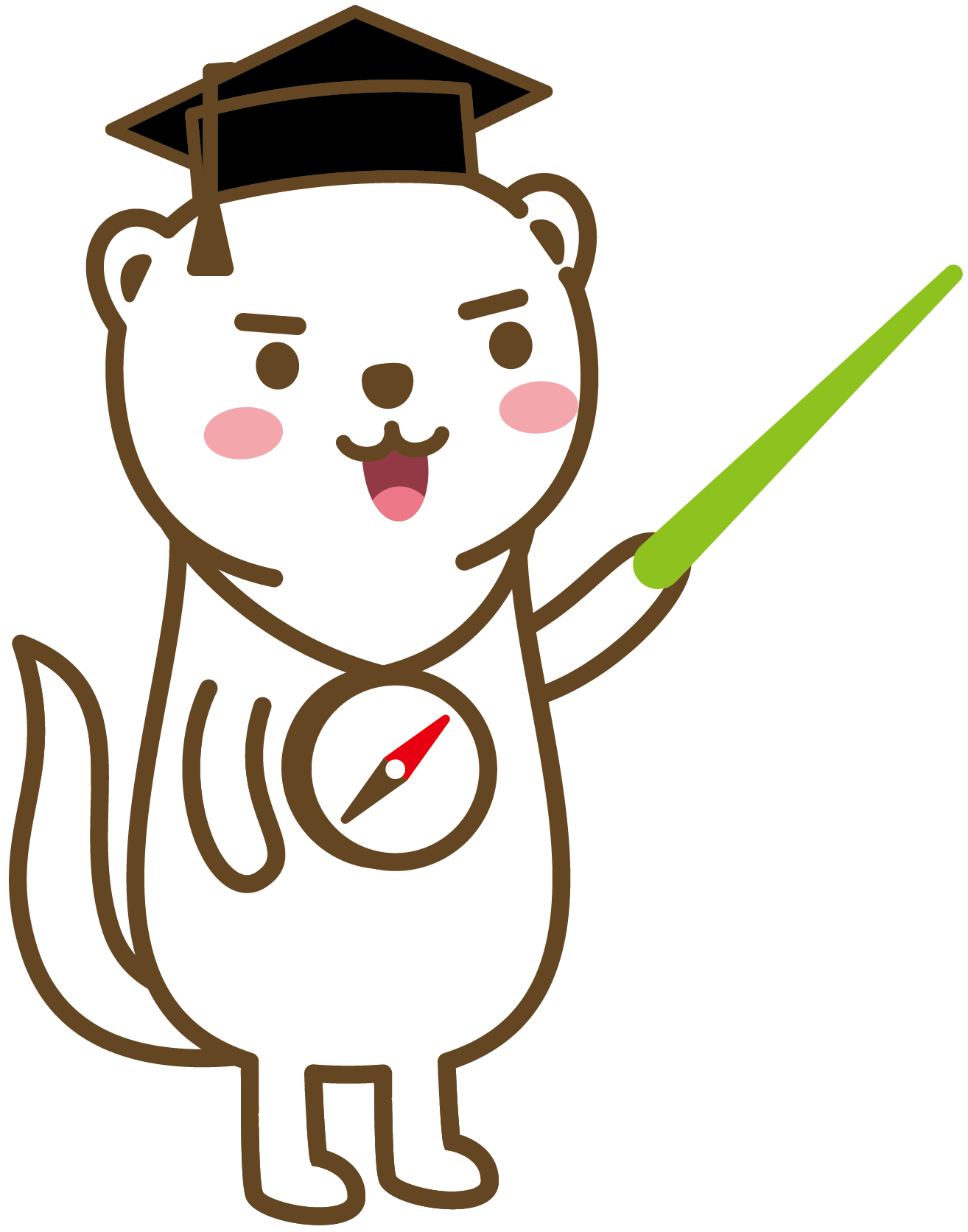
具体例
東京の弁護士に依頼したとします。
その事務所では、出張日当は半日拘束で3万円・1日拘束で5万円、出廷日当は1回2万円と設定されています。
この条件で、合計7期日かかり、6回は都内の事務所からWEBによる裁判期日、1回は尋問のために名古屋まで半日出張したとしましょう。
都内での6回分は出廷日当2万円×6回で12万円、名古屋出張分は出張日当3万円+出廷日当2万円で5万円となります。
結果として、日当の合計は17万円となります。
このように、弁護士の日当には一定の幅がありますので、委任の際に確認しておくといいでしょう。
弁護士の日当は相場が決まっているとはいえ、期日が増えたり出張が重なったりすると高額になりがちです。
だからこそ、依頼者が工夫することで費用を抑えることが重要です。
日当を節約できれば、全体の弁護士費用の負担も軽くなり、安心して依頼を続けることができます。
例えば、弁護士の日当を節約する方法としては、以下の3つがあります。
それでは、弁護士の日当を節約する具体的な方法について順番に見ていきましょう。
日当を抑える最もシンプルな方法は、できるだけ近くの弁護士に依頼することです。
遠方の弁護士に依頼すると、移動に伴う出張日当が追加されるため、費用が高くなりやすいからです。
例えば、東京に住んでいる方が大阪の弁護士に依頼した場合、裁判所が東京地裁であっても大阪からの移動のために出張日当が請求されるケースがあります。
一方で、地元の弁護士に依頼すれば、出張日当は不要となり、費用負担を大幅に抑えられます。
そのため、できるだけ居住地や裁判所に近い弁護士を選ぶことが節約につながります。
ただし、専門性の高い案件では、日当費用が高くなったとしても遠くの弁護士に依頼した方が結果的に良い解決になることがあります。
日当は裁判期日ごとに発生するため、期日が長引けば長引くほど費用は増えていきます。
したがって、早期解決を目指すことが日当の節約にも直結します。
例えば、尋問前の期日で和解により解決できれば、期日の回数は減りますし、出張も不要となり、判決となった場合に比べて日当も安くなることが多いです。
日当を抑えるためには早期に解決することを目指すといいでしょう。
裁判を起こす場合、どの裁判所が管轄になるかを確認しておくことも重要です。
遠方の裁判所で手続きを行うと出張日当も高くなりがちだからです。
例えば、被告の住所や所在地以外にも管轄がある場合があり、最寄りの裁判所に管轄があることもあります。
近くの裁判所に申し立てをすることができないかよく確認してみると良いでしょう。
弁護士に依頼する際には、日当だけでなく他の費用も必要となります。
費用の全体像を把握しておけば、依頼を検討する際に安心して判断できます。
例えば、弁護士の日当以外に発生する費用としては、以下のとおりです。
それでは、日当以外に発生する費用について順番に見ていきましょう。
着手金とは、弁護士に依頼を正式にお願いする段階で支払う費用です。
これは事件の結果にかかわらず返金されないのが原則で、弁護士が活動を始めるための基本的な対価とされています。
例えば、労働審判を申し立てる場合には、依頼時に10万円から数十万円程度の着手金を支払うケースがあります。
ただし、完全成功報酬制の事務所など着手金が必要な事務所も増えてきましたので探してみると良いでしょう。
弁護士の着手金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
報酬金とは、事件が成功に終わった場合に支払う成果報酬です。
勝訴や和解などで依頼者が得られた利益に応じて金額が決まるのが一般的です。
例えば、未払い残業代の請求で100万円を回収できた場合、その一部を報酬金として弁護士に支払うことになります。
報酬金は成果に応じた後払いの費用であるため、最終的な支払い総額に大きく影響する点に注意が必要です。
弁護士の成功報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。
法律相談料は、依頼前に弁護士へ相談する際に発生する費用です。
30分あたり5千円程度を目安とする事務所が多いですが、初回は無料で受けられる場合もあります。
例えば、初回相談無料を利用して複数の弁護士に相談すれば、費用をかけずに比較検討することができます。
相談料は少額ですが、複数回重なると合計で負担が大きくなるため、事前に確認しておくと安心です。
弁護士の法律相談料については、以下の記事で詳しく解説しています。
実費とは、弁護士活動に直接かかった費用を依頼者が負担するものです。
郵便切手代や収入印紙代、交通費、コピー代などがこれに含まれます。
例えば、裁判を起こす際には収入印紙代が必要となり、数千円から数万円かかる場合もあります。
実費は事務処理に欠かせないため、少額でも積み重なると意外に大きな負担になることがあります。
弁護士費用の実費については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士の日当についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.弁護士の日当には、消費税がかかります。
例えば、出廷日当が3万円と設定されている場合、実際の請求額は3万円に消費税が加算され、合計3万3千円となります。
したがって、契約時には「税抜きか税込みか」を確認しておきましょう。
A.支社が事業者である場合には、弁護士に日当を支払う際に源泉徴収が必要です。
日当から一定割合(10.21%など)を差し引き、残額を弁護士に支払うことになります。源泉徴収分は依頼者が税務署に納付する仕組みです。
例えば、日当が3万円の場合には3063円が源泉徴収され、依頼者が弁護士に支払うのは2万6937円となります。
A.弁護士の日当は、旅費交通費、支払報酬料、業務委託費など実態に応じて処理することになります。
A.弁護士の日当は、原則として裁判期日や出張の後に精算されることが多いです。
ただし、事務所によっては月末にまとめて精算する事務所、委任終了時にまとめて精算する事務所もあります。
依頼前に「どのタイミングで支払うのか」を確認しておくと安心です。
A.当番弁護士の日当は、1万円程度です。
ただし、弁護士会が支給するため原則として依頼者が支払う必要はありません。
なお、継続的な相談や依頼は別途有料の契約が必要となります。
弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、弁護士の日当とは何かを説明したうえで、相場や出張・出廷日当と消費税や節約方法3つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・弁護士の日当とは、裁判の期日などで弁護士が時間的に拘束されたことへの対価として支払う費用です。
・弁護士の日当の相場は、出張日当は3万円~10万円、出廷日当(出頭日当)は2万~5万円です。
・弁護士の日当を節約する方法としては、以下の3つがあります。
方法1:近くの弁護士に依頼する
方法2:早期解決を目指す
方法3:裁判所の管轄を確認する
・弁護士の日当以外に発生する費用としては、以下のとおりです。
費用1:着手金
費用2:報酬金
費用3:法律相談料
費用4:実費
この記事が弁護士の日当について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する
-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)
髙田晃央
髙田法律事務所
東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504
詳細はこちら

小藤貴幸
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

鴨下香苗
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

三部達也
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階
詳細はこちら
人気記事

2025年5月2日
法律一般
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日
法律手続
裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日
法律手続
債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。