!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/09/07
退職勧奨

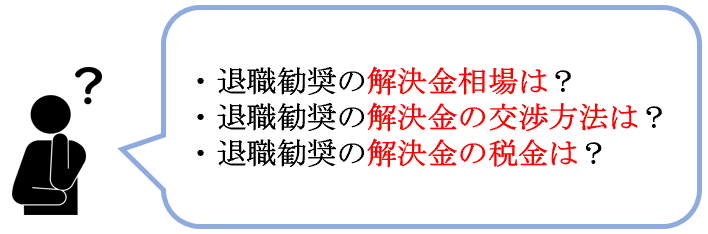
退職勧奨の解決金について知りたいと悩んでいませんか?
会社側から解決金を出すので退職してほしいと言われても、どうすればいいのか分からないという方も多いですよね。
退職勧奨の解決金とは、労働者が会社から退職するように言われた場合に、これに応じることの対価として支払われることになる金銭のことです。
会社から退職勧奨をされた際に、とくに解決金の提示がない場合には、安易に退職勧奨には応じないようにしましょう。
退職勧奨の解決金の相場は、賃金の3ヶ月分~6ヶ月分程度です。
退職勧奨の解決金を交渉する場合には、会社から言われるままになるのではなく、焦らず冷静に対等な立場で交渉をしていく必要があります。
退職勧奨の解決金については、特別退職金との名目で退職所得として処理されることが多いですが、支払いの経緯や性質によっては和解金として一時所得として処理される可能性もあります。
実は、退職勧奨の解決金については、交渉力次第で獲得できる金額も大きく変わってきます。交渉した人にだけ増額して、交渉しなかった人は十分な解決金をもらえないということもあります。
この記事をとおして、多くの労働者の方に退職勧奨の解決金について知っていただき損をしてしまう方が出なくなれば幸いです。
今回は、退職勧奨の解決金相場を説明したうえで、解決金なしは違法かどうか、簡単な交渉方法4つと税金を解説していきます。
この記事でわかることは、以下のとおりです。
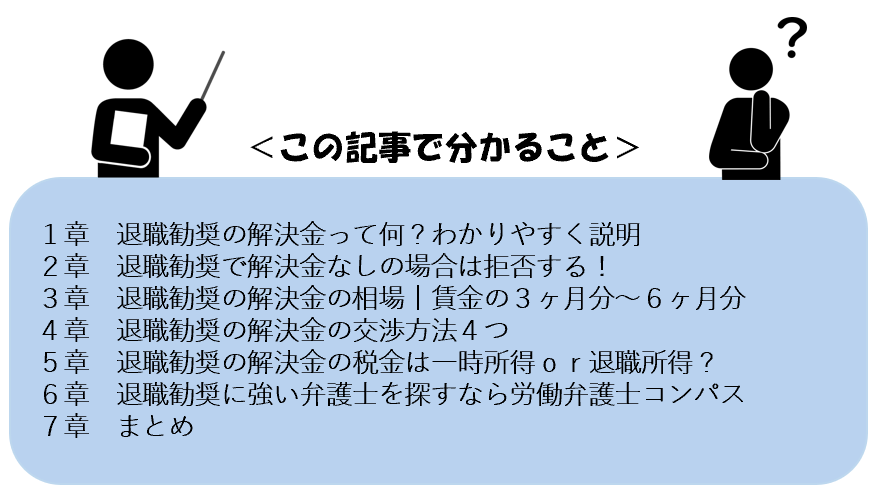
この記事を読み終わったら、適正な退職勧奨の解決金を獲得するにはどうすればいいのかがよく分かるようになっているはずです。
退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下の動画で詳しく解説しています。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

退職勧奨の解決金とは、労働者が会社から退職するように言われた場合に、これに応じることの対価として支払われることになる金銭のことです。
退職勧奨の際には、紛争化していない場合もあり、解決金と言う言葉ではなく、正しくは特別退職金と言う言葉が使われることが多いです。
退職勧奨とは、会社側は、労働者に自主的に退職するように促すことをいいます。
会社側は、労働者に対して、解決金の支払いを行う法的義務があるわけではありませんが、労働者に退職に応じてもらう材料として解決金を提示することがあるのです。
例えば、ある日、社長や人事からミーティングを設定されることがあります。
そして、ミーティングに参加すると雇用を継続できない旨を伝えられ、退職日や解決金等が記載された退職合意書を見せられ、サインするように求められます。
このように退職勧奨の解決金と言うのは、会社側が労働者に退職してもらうために提示する金銭です。
退職勧奨の特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨で解決金なしの場合には、退職に応じることを拒否するようにしましょう。
労働者が無条件で退職に応じるメリットがないことが多いためです。
例えば、もし労働者が退職を検討している場合であっても、退職のタイミングは労働者自身で選べた方が、キャリアや生活への負担が少なく済みます。
そもそも、期間の定めのない契約であれば、定年まで働き続けることもできる以上、無理して転職活動を行う必要自体ありません。
もし、会社から解雇される場合でも、会社は30日前の解雇予告を行う必要がありますし、不当解雇となれば多額のバックペイを請求できる可能性もあります。
このように労働者が無条件で退職勧奨に応じるメリットが乏しいことが多いので、解決金なしの場合には安易に応じず、拒否することを検討するべきなのです。
ただし、懲戒解雇をされてしまうと、経歴に傷がついてしまったり、退職金が支払われなかったりすることがあります。
そのため、多額の金銭を横領した場合など、懲戒解雇をされたらこれが有効になってしまう可能性が高い事案では、解決金なしでの退職に応じることも検討に値することがあります。
退職勧奨の解決金の相場は、賃金の3ヶ月分~6ヶ月分程度です。
退職勧奨の解決金については法律上で支給が義務付けられているものではないので、当然その金額についても決まりがあるものではありません。
解決金については労働者と会社が交渉をしていく中で決まっていくものです。
例えば、転職期間の平均が4ヶ月程度とされており、3ヶ月分~6ヶ月分の賃金が支給されると労働者の転職への不安が一定程度緩和されることになります。
もっとも、解雇される場合でも、30日分の解雇予告が必要ですし、有給休暇の残日数などもありますので、1~2ヶ月程度では応じるメリットを感じない労働者が多いです。
会社側は、現時点で解雇を行っているわけではなく、裁判所から解雇が不当であると言われたわけでもないため、1年分近い解決金などには簡単に応じない傾向にあります。
このような交渉の結果として、賃金の3ヶ月分~6ヶ月分で話し合いがまとまることが多いということになります。
ただし、最終的には、労働者がどの程度その会社で働き続けたいと考えているか、会社側がどの程度その労働者に退職してほしいと考えているか等で金額は大きく変わってきます。
外資系企業などでは、1年を超える特別退職金が提示されることも珍しくなく、役職が高い方や勤続年数が長い方には2年近い金額が提示されることもあります。
退職勧奨の解決金を交渉する場合には、会社から言われるままになるのではなく、焦らず冷静に対等な立場で交渉をしていく必要があります。
会社側はなるべく解決金の金額を低く抑えようしますので、労働者が何も言わずに応じてしまうと適正な金額にはならないためです。
具体的には、退職勧奨の解決金の交渉方法については、以下の4つがあります。

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。
退職勧奨の解決金を交渉したい場合には、まずは退職合意書にサインせず持ち帰るようにしましょう。
一度、退職合意書にサインをしてしまうと後から撤回することが容易ではないためです。
会社は、労働者が退職合意書にサインをした時点で目的を達成してしまいますので、それ以降は解決金の交渉にも応じなくなります。
例えば、「弁護士に相談したいので、一度持ち帰らせていただきます。」とだけ回答して、サインをせずに持ち帰るようにしましょう。
退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。
次に、退職合意書を持ち帰ってきたら、その退職合意書をもって弁護士に相談に行きましょう。
退職勧奨への対応は法的な見通しを分析したうえで、適切な方針を立てて、一貫した対応を行っていくことが成功の秘訣だからです。
とくに、会社側は顧問弁護士に相談しながら退職勧奨を行っていることが多く、労働者の一挙手一投足を観察しています。
労働者が会社と対等な立場で交渉していこうと考えた場合には、労働者も法律の専門家のサポートを受けることがおすすめです。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。専門性が高い分野であるため、労働問題に注力していて、退職勧奨対応に実績のある弁護士を探すようにしましょう。
次に、方針が決まったら、通知書を送付し会社と協議しましょう。
会社側からの退職勧奨について、あなたの立場や考えを示すことが交渉の出発点となります。
法律や判例の考えなどを指摘しつつ、適正な金額になるように会社側を説得していくことになります。
弁護士に依頼する場合には一貫した主張になるように、弁護士に通知書を送ってもらった方が良いでしょう。
相談前に通知書を送ってしまいリカバリーが難しくなってしまうことも多いためです。
最後に、話し合いが折り合わず、会社側が解雇を強行してきたり、嫌がらせをしてきたりする場合には、労働審判や訴訟を提起することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。
審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。
退職勧奨の解決金については、特別退職金との名目で、退職所得として処理されることが多いです
解雇前の退職勧奨の段階では、会社側が具体的な法律行為を行ったわけではなく、紛争化しているわけではないことが多いためです。
社会保険料は源泉されず、税金についても給与所得に比べると有利な取り扱いとなる傾向にあります。
とくに勤続期間が5年を超える方の場合は、給与に比べて節税効果が高い傾向にあります。
ただし、退職勧奨の解決金についても、退職強要やハラスメントなどの慰謝料を請求しているような場合などには、和解金との名目で一時所得として処理される可能性もあります。
不法行為や債務不履行による損害賠償を請求している場合には紛争化しており、その紛争を解決するための対価と見る余地もあるためです。
一時所得の場合には、会社側は源泉をせずに労働者に振り込みを行うことになり、労働者自身で確定申告を行うことになります。
一時所得についても、給与所得に比べると節税効果が高い傾向にあります。
なお、最終的にどのように課税されるかについては、税務署が実態により判断することになります。
退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、退職勧奨の解決金相場を説明したうえで、解決金なしは違法かどうか、簡単な交渉方法4つと税金を解説しました。
この記事で説明したことをまとめると以下のとおりです。
この記事でお伝えしたことが、退職勧奨の解決金について知りたいと悩んでいる方の役に立てばうれしいです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。