!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/11/24
退職勧奨

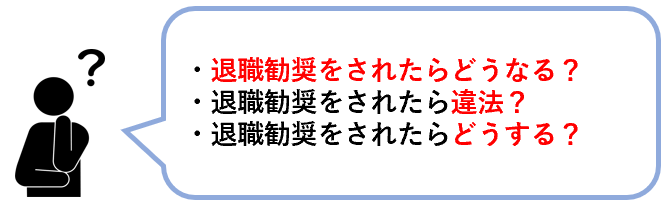
会社から退職勧奨をされてしまいどうすればいいのかが困っていませんか?
いきなり退職するように言われても、生活やキャリアへの不安もありますので納得することはできませんよね。
退職勧奨をされたら、会社から退職合意書にサインをするように説得が繰り返されることになります。
退職勧奨をされた場合には知っておいていただきたいリスクがいくつかあります。
あなたが退職勧奨をしないでほしいと言っているにもかかわらず、会社側が執拗に退職するよう説得してくる場合には、違法となる可能性があります。
もし、あなたが、不安がなくなれば退職に応じることを検討しても良いと考えている場合には、交渉すべき退職条件がいくつかあります。
いずれにせよ会社から退職勧奨をされた場合には、焦らず冷静に、方針を決めてから一貫した対応を行っていく必要があります。
退職勧奨への対応は専門的な部分も多く、労働者の一つ一つの言動や態様が結果に大きく影響するため、会社と対等に交渉するためには、弁護士に依頼することがおすすめです。
実は、会社から退職勧奨をされた際に焦って不利な発言や態様をしてしまう方が多く、もっと早く相談していただきたかったと感じることが少なくありません。
この記事をとおして、会社から退職勧奨をされた方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、退職勧奨されたらどうなるかを説明したうえで、退職勧奨をされた場合のリスクやどうすればいいのか簡単な対処手順4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
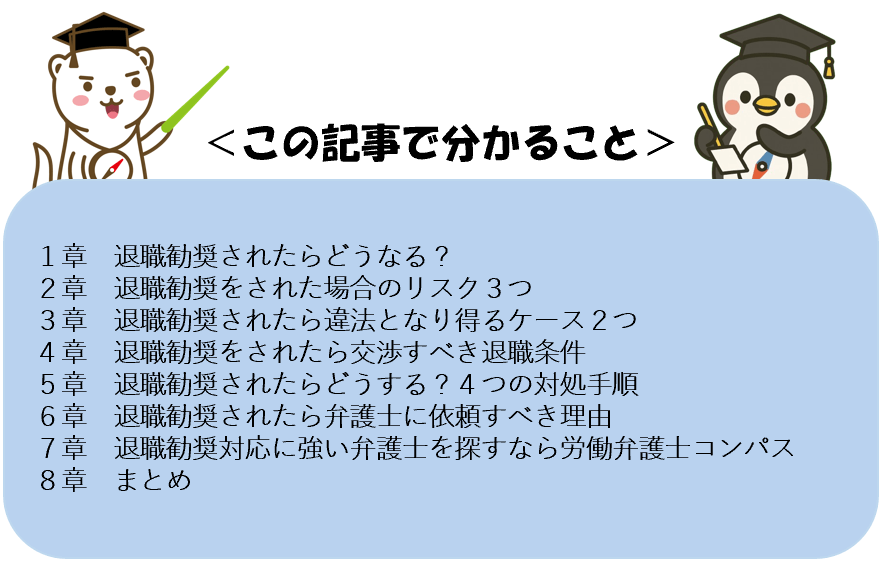
この記事を読めば、退職勧奨をされたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下の動画で詳しく解説しています。
退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下のショート動画でも1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

退職勧奨をされたら、会社から退職合意書にサインをするように説得が繰り返されることになります。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職するように促すことを言います。
あくまでも労働者に対して同意するよう説得するものにすぎませんので、労働者の同意なく一方的に退職させる解雇とは異なります。
例えば、退職勧奨をされたら以下のような流れで進んでいくのが通常です。
ある日、人事や上司から詳細は伝えられずにミーティングを設定されます。最近では面談室で行われる場合だけではなく、オンラインにより行われることも多いです。
ミーティングの場に行くと人事と上司がいて、「あなたを雇用し続けることは難しいとの判断になった。退職してほしい。」と切り出されます。
理由は、会社の業績が良くなく人員整理の必要があると言われたり、パフォーマンス不足と言われたり、社風に合わないと言われたり、端的に説明される傾向にあります。
そして、退職合意書を示されながら退職日などの条件を説明されます。
その場でサインを求められることもありますし、期限内に回答をするようにと言われることもあります。
労働者が退職勧奨に応じない場合には、1週間程度ごとにミーティングを設定され、検討状況の確認が行われ、説得が繰り返されます。
退職勧奨中は自宅待機を命じられ仕事を外されるような場合もあります。
退職勧奨をされた場合には知っておいていただきたいリスクがいくつかあります。
リスクを知っておくことで適切な対処を行いやすくなります。
例えば、労働者が退職勧奨をされた場合のリスクとしては、以下の3つです。

それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。
退職勧奨をされた場合のリスクの1つ目は、不当な条件で退職させられることです。
会社は労働者の無知に付け込んで、不当な条件での退職合意書にサインをさせることが少なくないためです。
例えば、2025年7月15日に退職勧奨をされて、退職合意書に2025年7月31日をもって自己都合により退職することを確認すると記載されていたとしましょう。
労働者は拒否できないとおもって、この退職合意書にその場でサインをしてしまったとします。
一度、退職合意書にサインをしてしまうと、後から撤回することは容易ではありません。
裁判所に持っていっても、大人が自分でサインしているのだから、当然、内容は理解していたでしょうとドライなことを言われてしまうことも少なくありません。
仮に、退職合意書にサインしなければ、残っている有給休暇を消化したうえで退職することもできたかもしれませんし、ゆっくり転職先を探すこともできたかもしれません。
このように退職勧奨された際に会社の言いなりになってしまうと不当な条件で退職させられてしまうリスクがあります。
退職勧奨をされた場合のリスクの2つ目は、嫌がらせをされて居づらくなることです。
会社は、労働者が退職に応じない場合には、嫌がらせをして労働者が退職せざるを得ない状況に追い込んでくることがあります。
例えば、嫌な仕事を振られたり、無視されたり、給料を減額されたりと言ったような場合です。
ただし、法律では、会社は、労働者の職場環境に配慮する義務がありますし、合理的な理由なく一方的に労働条件を不利益に変更することも制限されています。
そのため、会社側から嫌がらせをされた場合でも、自身の法的な権利を主張していくことが大切です。
退職勧奨をされた場合のリスクの3つ目は、解雇されることです。
会社は、労働者が退職勧奨に応じない場合には、解雇をしてくることがあります。
仮に解雇が有効となってしまうと、解雇日をもって退職したものとして扱われてしまうことになります。
ただし、解雇は労働者の同意がいらない代わりに、厳格な法的な規制があります。
そのため、退職勧奨されたら、解雇できる事案なのかどうか弁護士に相談するようにしましょう。
解雇されたらどうなるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
あなたが退職勧奨をしないでほしいと言っているにもかかわらず、会社側が執拗に退職するよう説得してくる場合には、違法となる可能性があります。
退職勧奨は、労働者の意思を無視して行っていいものではありませんし、労働者は働きやすい職場環境で働く利益を有しているためです。
具体的には、退職勧奨をされたら違法となり得るケースとしては以下の2つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
退職勧奨をされたら違法となり得るケースの1つ目は、退職強要に該当する場合です。
退職強要とは、労働者の意思に反して、退職するよう強制することです。
退職勧奨を行う際には、あくまでも労働者の自主的な退職意思の形成を促すに際し、社会通念上相当と認められる限度で行わなければならないとされています。
労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、名誉感情を害するようなことを言ったりすることは、許されません。
(参照:東京地判平成23年12月28日労経速2133号3頁[日本アイ・ビー・エム事件])
例えば、退職勧奨中に机を叩いて威圧したり、労働者が退席したいと繰り返し言っているのに3時間以上にわたり退職勧奨を継続したりするような場合には、違法となる可能性があります。
退職勧奨をされたら違法となり得るケースの2つ目は、パワハラに該当する場合です。
職場におけるパワーハラスメントは許されず、会社はこのようなことが行われないように措置を行う義務があります。
例えば、退職勧奨において人格を否定するような発言が行われた場合には、精神的な攻撃として職場におけるパワハラに該当する可能性があります。
退職勧奨を拒否して働かせてほしいと言っているのに、仕事を与えない状況を継続する場合も、人間関係からの切り離しや過小な要求としてパワハラに該当する可能性があります。
パワハラの慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
もし、あなたが、不安がなくなれば退職に応じることを検討しても良いと考えている場合には、交渉すべき退職条件がいくつかあります。
あなた自身の生活やキャリアを守る必要があるためです。
例えば、退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件としては、以下の5つがあります。

それでは、これらの条件について順番に説明していきます。
退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件の1つ目は、特別退職金です。
特別退職金とは、会社が退職勧奨に応じる対価として通常の退職金とは別に支給するものです。
退職金制度がない会社でも支給される可能性がありますし、退職金制度がある会社では通常の退職金に加えて支給される可能性があります。
特別退職金の相場は、給料の3か月分~6か月分程度です。
特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件の2つ目は、ガーデンリーブです。
ガーデンリーブとは、退職日までの就労免除期間のことです。
在籍しながら転職活動に集中することができ、給料が支払われるので生活への不安も払拭できます。
ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件の3つ目は、有給買取です。
会社は、労働者の有給の残日数がある場合でも、必ずしもこれを買い取る義務があるわけではありません。
ただし、労働者が有給の買い取りがされない限り、退職に応じないこともまた自由です。
有給消化と有給買取はどっちが得かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件の4つ目は、会社都合退職です。
退職勧奨により離職する際には、会社都合退職として処理されることになります。
ハローワークインターネットサービスでも、特定受給資格者の範囲に含まれる者として、「退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」が挙げられています。
ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
退職勧奨をされたら交渉すべき退職条件の5つ目は、再就職支援です。
会社側は、退職勧奨の際に人材紹介会社と契約して、退職する労働者に対して再就職支援サービスを提供しようとしてくることがあります。
労働者側からあえて積極的に獲得を目指していくような条件ではありませんが、会社が提示してくるようであればあえて拒否する必要まではありません。
ただし、退職合意書を締結する前に再就職支援サービスを利用することは控えた方がいいでしょう。
会社から退職勧奨をされた場合には、焦らず冷静に、方針を決めてから一貫した対応を行っていく必要があります。
よく考えずに会社から言われるがまま応じてしまったら会社側の思うツボですし、自分自身の権利を守ることもできません。
具体的には、退職勧奨をされたら以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
退職勧奨をされた場合の対処手順の1つ目は、退職合意書にサインせず持ち帰ることです。
一度、退職合意書にサインをしてしまうと、後から撤回することは容易ではありません。
会社は、退職合意書にサインをしてもらった時点で目的を達成してしまいますので、それ以降は退職条件の交渉などにも応じてくれなくなります。
また、退職の合意は、退職合意書にサインをしなくても、口頭の発言やメール、チャットでも成立してしまう可能性がありますので、発言にも注意する必要があります。
退職勧奨をされてもその場で退職合意書の内容を正確に理解することは困難です。
「弁護士に相談したいので一度持ち帰ります」とだけ答えて、その場ではサインせずに一度退職合意書を持ち帰るようにしましょう。
退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨をされた場合の対処手順の2つ目は、弁護士に相談することです。
退職勧奨にどのように対応していくかは、法的な見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、方針を策定し、一貫した対応を行っていく必要があります。
一度行った対応や発言を後から撤回することは難しいので、早い段階で弁護士に助言をしてもらうことが大切です。
退職勧奨をされた場合の対処手順の3つ目は、通知書を送付することです。
退職勧奨をされて労働者が何もしないでいると、労働者が退職に異論を唱えていなかったと言われたり、次のステップに進められてしまったりする可能性があります。
そのため、退職勧奨に対してどのように対応していくか方針を決めたら、会社に対して、通知書を送付するようにしましょう。
ただし、弁護士に依頼する際には、弁護士に代わりに通知書を送ってもらうことをおすすめします。
通知書の記載内容等について揚げ足をとられてしまったり、通知書の記載内容がその後の交渉に影響を与えたりしてしまうことが多いためです。
退職勧奨をされた場合の対処手順の4つ目は、交渉することです。
通知書に対して会社側から回答があったら、お互いの立場が明らかになりますので、話し合いにより解決することが可能かどうか協議してみましょう。
適切に交渉していくことで、早期に少ない負担で良い解決をすることができる可能性があります。
退職条件の交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨をされたら、その対応については弁護士に依頼することがおすすめです。
退職勧奨への対応は専門的な部分も多く、労働者の一つ一つの言動や態様が結果に大きく影響するためです。
会社は、顧問弁護士に相談しながら退職勧奨を進めていることが多く、労働者も会社と対等に交渉するためには、法律の専門家によるサポートを受けるべきです。
退職勧奨事案で難しいのは、複数の法的な可能性があることです。想定される可能性に応じて、適切な法的な見通しと対策を検討しておく必要があります。
ただし、退職勧奨への対応は、専門的であり弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題に注力していて、退職勧奨対応に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
退職勧奨対応に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、退職勧奨されたらどうなるかを説明したうえで、退職勧奨をされた場合のリスクやどうすればいいのか簡単な対処手順4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が会社から退職勧奨をされてしまいどうすればいいのかが困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

鴨下香苗
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階
詳細はこちら

鈴木晶
横浜クレヨン法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

森江悠斗
森江法律事務所
東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル3階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。