!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/12/17
不当解雇

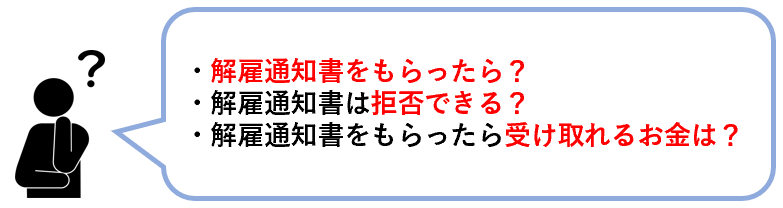
会社から解雇通知書をもらったものの拒否できないか悩んでいませんか?
いきなり解雇通知書をもらっても、生活やキャリアもあるので退職することに不安を感じている方も多いですよね。
解雇通知書をもらったら、拒否することはできませんが、不当解雇であることを理由に争うことができます。
解雇通知書をもらったら、解雇日と解雇理由、根拠となる就業規則を確認するようにしましょう。
解雇通知書をもらった場合には、会社に対して、いくつのお金を請求できる可能性があります。
もし、会社から解雇通知書をもらった場合も、あなた自身の権利を守るために焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。
会社から解雇通知書が交付されない場合には、会社に対して解雇したこと示す書面を交付するよう促すことが考えられます。
実は、解雇通知書をもらった場合には、どのように対応していくかによって結果が大きく変わってくる可能性があります。
焦って行動してしまったり、何もせずに放置してしまったりしたことによって、不利になってしまうことも少なくありません。
この記事をとおして、会社から解雇の通知書をもらった方々に是非知っておいたいただきたいことをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、解雇通知書をもらったら拒否できるかを説明したうえで、重要確認事項と簡単な対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
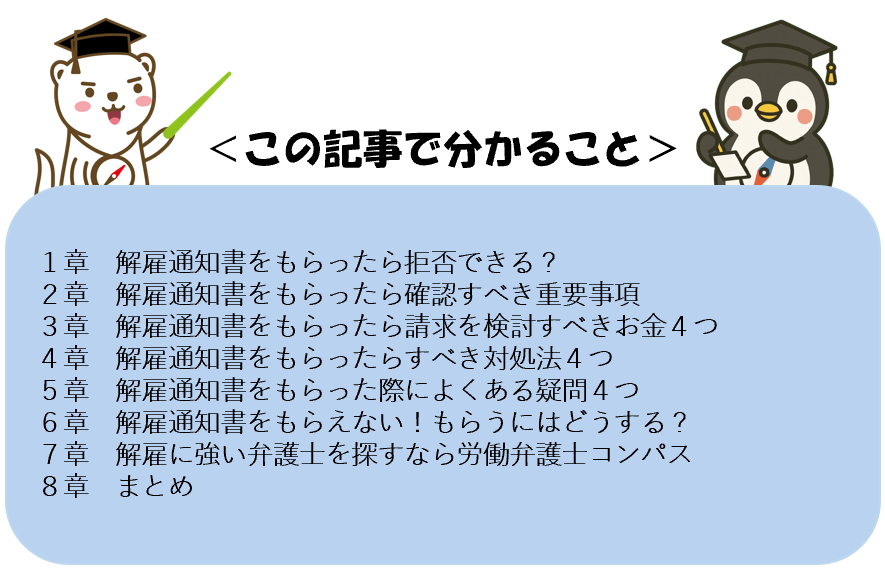
この記事を読めば、解雇通知書をもらった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
解雇通知書をもらったら拒否できるかについては、以下のショート動画でも60秒程度でまとめています。時間がない方は是非コチラをご覧ください。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

解雇通知書をもらったら、拒否することはできません。
なぜなら、解雇とは、会社が一方的に労働者を退職させること言いますので、労働者の同意は必要とされていないためです。
例えば、労働者が解雇通知書をもらった際に、「納得できないので解雇を拒否します!」と言ったとしても、会社から「解雇に労働者の同意はいらない」と言われてしまいます。
ただし、解雇については、労働者の同意がない代わりに、厳格な法律の条件を満たさなければなりません。
解雇は法律上の条件が満たされていない場合には、濫用として無効となります。
そのため、労働者は、解雇通知書をもらったら、拒否はできなくても、不当解雇であり濫用として無効であると争うことができるのです。
解雇通知書をもらったら、確認すべき事項がいくつかあります。
冷静に解雇通知の内容を理解することで法的な見通しや自分が置かれている状況について、正確に理解することができます。
具体的には、解雇通知書をもらった場合には、以下の事項を確認するようにしましょう。
それでは、これらの事項について順番に説明していきます。
解雇通知書をもらった際の確認事項の1つ目は、解雇日です。
解雇日を見ることで、何月何日に退職の処理をされることになるのかを知ることができます。
解雇日までについては、あなたが労働者としての地位にあることに争いはないことになります。
解雇通知書をもらった際の確認事項の2つ目は、解雇理由です。
解雇理由を見ることで、解雇が法的に不当かどうかの見通しを立てやすくなります。
また、解雇を争う際にどのような主張や証拠を準備すればよいのかが分かります。
もし、解雇理由が不明確な場合には、解雇理由証明書を交付するように求めましょう。
解雇理由証明書とは、文字通り、解雇の理由が記載された書面のことです。
会社は、解雇した労働者から解雇理由証明書を求められた場合には、労働基準法上、これを交付する義務があります。
解雇理由証明書の請求の仕方については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇通知書をもらった際の確認事項の3つ目は、根拠となる就業規則です。
就業規則、労働者と会社との間の労働条件の最低基準を規定するものです。
会社側が根拠とする就業規則に該当しない場合には、解雇が不当になる可能性があります。
そのため、根拠となる就業規則を確認することにより、法的な見通しを立てやすくなるのです。
解雇通知書をもらった場合には、会社に対して、いくつかのお金を請求できる可能性があります。
法律や判例、会社の規則により、労働者の権利が保護されているためです。
具体的には、解雇通知書をもらったら請求を検討すべきお金としては、以下の4つがあります。

それでは、これらについて順番に説明していきます。
解雇が不当な場合には、バックペイを請求できる可能性があります。
バックペイとは、不当な解雇をされた日から解決日まで遡って支払われることになる給料のことをいいます。
解雇が不当である場合には、解雇日以降、労働者が出社することができなかった原因は会社側にあることになります。
例えば、2025年7月末に解雇された場合において、2026年7月末に解雇が不当とされた場合には、1年分の給料が遡って支払われる可能性があります。
バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。
バックペイについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
解雇が不当なだけではなく、悪質性が高い場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
労働者の権利を違法に侵害するものとして、不法行為に該当することがあるためです。
不当解雇による慰謝料の相場は、50万円~100万円程度と言われています。
ただし、従業員としての地位とバックペイが認められた場合には、労働者の精神的苦痛も癒えると考えられており、慰謝料まで認められるには特段の精神的苦痛が必要です。
不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
30日前の解雇予告が行われていない場合には、解雇予告手当を請求できる可能性があります。
会社は、労働基準法上、原則として解雇の30日前に予告する必要があり、予告をしない場合には不足する日数に相当する手当を支払う必要があるとされているためです。
ただし、解雇予告手当の支払いを受けることができるのは、解雇が有効な場合です。
不当解雇であるとしてバックペイを請求する可能性がある場合には、解雇予告手当を請求することは矛盾した態様になるリスクがありますので注意が必要です。
解雇予告手当をもらえない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職金規程があり支給要件を満たしている場合には、退職金を請求できる可能性があります。
退職金については、法律上、支払いの義務が定められているわけではありません。会社ごとに退職金制度が定められます。
会社を退職する際には、退職金規程を確認して、退職金の支給を受けることができるかどうか確認するといいでしょう。
ただし、退職金は、退職する場合に支給されるものであり、不当解雇を争う際には、退職金を請求することは矛盾した態様になるリスクがありますので注意が必要です。
もし、会社から解雇通知書をもらった場合も、あなた自身の権利を守るために焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。
あなたが何もしなければ、会社は不当解雇であっても有効であることを前提に手続きを進めてくるためです。
具体的には、解雇通知書をもらったらすべき対処手順としては、以下の4つです。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
解雇通知書をもらったらすべき対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです。
法的な見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、事案に応じた方針を助言してもらうようにしましょう。
不当解雇についての手続きは専門的となり、一貫した対応を行っていくことが大切となりますので、最初から弁護士にサポートしてもらうことがおすすめです。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、不当解雇事案に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
解雇通知書をもらったらすべき対処手順の2つ目は、通知書を送付することです。
解雇された後に何もせずに放置すると、働く意思を失っていたと指摘されるなどして、不当解雇と認められてもバックペイを請求できなくなってしまうことがあります。
そのため、解雇通知書をもらったら、早い段階で、解雇は濫用として無効である旨を記載した通知書を送付することで、不当解雇を争うことを明確にしておくといいでしょう。
ただし、通知書は証拠として裁判所に出されることも多いもので、細かい表現などで揚げ足を取られることもあるので、弁護士に代わりに送ってもらうようにしましょう。
解雇通知書をもらったらすべき対処手順の3つ目は、交渉することです。
会社側からの回答があったら争点が明らかになりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみましょう。
示談が成立すれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をできる可能性があります。
解雇通知書をもらったらすべき対処手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。
審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。
不当解雇の訴訟については、以下の動画でも詳しく解説しています。
解雇通知書をもらった際によくある疑問としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A:安易にサインせず一度も持ち帰り弁護士に相談しましょう。
解雇通知書は、第1章で説明したように、労働者の同意を前提とした手続きではありません。
何についてのサインを求められているのか慎重に判断する必要があり、サインすることについて労働者にリスクはあれば、メリットがあるケースはほとんどありません。
一度、サインしてしまうと、後から、サインを撤回することは容易ではありません。
解雇通知書を交付されて、その場で冷静な判断を行うことは困難であるため、一度サインせず持ち帰るようにしましょう。
A:安易に退職届は出さないようにしましょう。
解雇通知書は、労働者の意思とは関係なく、会社が労働者を一方的に退職させるものです。
解雇された場合に労働者が退職届を出すことは想定されていません。
むしろ、退職届を出してしまうことにより、解雇ではなく、労働者が自ら退職したと主張されてしまい、不当解雇を争うことが難しくなってしまう可能性が高いです。
そのため、解雇通知書をもらっても、安易に退職届を出さないようにしましょう。
A:大きな違いはありません。
30日前の解雇予告を行っていることを明確にする趣旨で、30日前に通知する際には解雇予告通知書と記載されることがあります。
A:解雇通知書をもらったら、失業保険は原則として会社都合となります。ただし、重責解雇の場合には自己都合となります。
重責解雇とは、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を言います。
会社都合退職の場合には、失業保険の受給要件や給付日数等について自己都合よりも有利に扱ってもらうことができます。
解雇と失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社から解雇通知書が交付されない場合には、会社に対して解雇したこと示す書面を交付するよう促すことが考えられます。
解雇通知書がない状態ですと、後から解雇していないと言われることもあり、法律関係が不安定な状況となってしまうためです。
具体的には、解雇通知書をもらえない場合の対応としては、以下の3つが考えられます。

それでは、これらの対応について順番に説明していきます。
会社から「解雇」という単語が明確に出されていない場合には、解雇通知書が交付されるまで出勤するようにしましょう。
会社から解雇と明確に言われていないにもかかわらず、労働者が出勤することをやめてしまうと、無断欠勤をしていると指摘されることになります。
例えば、会社から自主的に退職してはどうかと言われた場合でも、これは退職勧奨に過ぎず、通常、解雇には該当しません。
そのため、会社から「解雇」と言う明確な単語が出ていないような場合には、自分の判断で解雇と断定せず、通常どおり勤務を継続するようにしましょう。
もし、本当に会社側があなたに退職してほしいと考えている場合には、解雇通知書が交付されることになります。
明日から来なくていいよと言われた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社から解雇と言う発言がされた場合には、録音又はスクリーンショットするようにしましょう。
解雇については、必ずしも、解雇通知書で行わなければいけないものではないため、口頭やチャット、メールなどでも、効力が生じます。
そのため、解雇するとの発言を録音したり、「解雇する」との記載があるメールやチャットをスクリーンショットしたりすることが考えられます。
会社から解雇と言われたものの録音やスクリーンショットをできなかった場合には、解雇理由証明書を請求しましょう。
解雇した会社は、労働基準法上、労働者からの求めに応じて、解雇理由証明書の交付をすることが義務付けられているためです。
解雇理由証明書の交付を受けることで、解雇されたことの証拠にもなります。
解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、解雇通知書をもらったら拒否できるかを説明したうえで、重要確認事項と簡単な対処法4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が会社から解雇通知書をもらったものの拒否できないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

小藤貴幸
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階
詳細はこちら

三部達也
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階
詳細はこちら

鈴木晶
横浜クレヨン法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303
詳細はこちら

鴨下香苗
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。