!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/10/13
労働一般

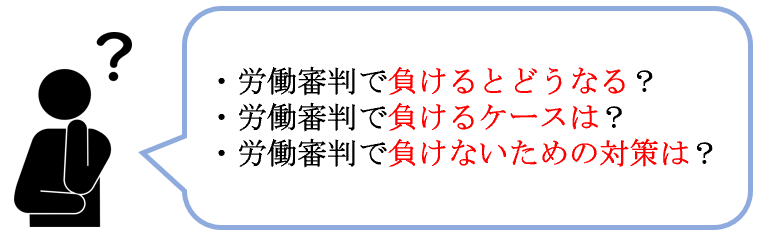
労働審判を申し立てたいと考えているものの負けたらどうなってしまうのか不安に感じていませんか?
労働審判で負けてしまうと自分に大きな不利益があるのではないかと心配になってしまいますよね。
労働審判で負けた労働者とは、労働審判委員会から不利な心証を示された労働者や請求を棄却するとの審判をされた労働者のことをいいます。
労働者が労働審判で負けてしまうのは、労働者の請求に十分な理由がないと判断されてしまったケースです。
労働審判で負けた労働者のリスクについては、労働者の取る行動によっても変わってきます。
会社は、労働審判で労働者が負けた場合であっても、そのこと自体を理由として、労働者に対して、損害賠償を請求することは難しいです。
労働審判で労働者が負けないためには、十分な準備と労働審判での適切な対応が必要になります。
実は、労働者は強く保護されていると言っても、常に労働者が勝つことができるというわけではなく、良い結果は知識や経験、努力、工夫があって得られるものです。
この記事をとおして、労働審判で負けることを不安に感じている労働者の方々に、誰でもイメージしやすいように分かりやすく必要な知識やノウハウをお伝えすることができれば幸いです。
今回は、労働審判で負けた労働者はどうなるかについて、3つのリスクと簡単な対策を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、労働審判で労働者が負けないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
労働審判で負けた労働者はどうなるのかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

労働審判で負けた労働者とは、労働審判委員会から不利な心証を示された労働者や請求を棄却するとの審判をされた労働者のことをいいます。
労働審判は全3回の期日で調停による解決を目指す手続きです。
第1回期日の前半30分~1時間程度で事実関係の確認などが行われます。
そして、第1回期日の後半では、確認した事実関係に基づいて、裁判所(労働審判委員会)の心証が示されるのが通常です。
労働審判は相手方がいる手続ですので、勝ち負けがあり、労働者にとって望ましくない結論になってしまうこともあります。
このように労働者の請求は難しいのではないかと言われてしまったり、請求を認めないとの審判を下されてしまったりして、負けてしまうこともあるのです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。
労働者が労働審判で負けてしまうのは、労働者の請求に十分な理由がないと判断されてしまったケースです。
労働者の請求がないとされてしまう理由は事案によって異なります。
例えば、労働審判で労働者が負けるケースとしては、以下の3つです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
労働審判で労働者が負けるケースの1つ目は、十分な証拠がない場合です。
裁判所は、あなたの請求が認められるかを証拠に基づいて判断していくことになります。
会社側とあなたの主張が対立している場合には、どちらの言っていることが正しいのか証拠によらなければ判断が難しいためです。
あなたが自分の記憶に基づいて正しいことを言っているつもりであっても、証拠がなければ、裁判所には信じてもらえないことがあるのです。
労働審判で労働者が負けるケースの2つ目は、法律構成自体に無理がある場合です。
労働審判では、裁判所が、法律に基づいて、あなたの権利が認められるかどうかを判断していきます。
あなたが自分では正しいと感じる主張を記載したとしても、法律や判例などの根拠がなければ請求は認められません。
例えば、よくあるのが本人訴訟などで、請求の根拠や請求が認められる条件を理解しないまま、申立書を記載しているような場合です。
労働者が頑張って、会社のコンプライアンスに問題があったり、ブラック企業であったりと言ったことを主張したとしても、それだけでは請求は認められないのです。
労働審判で労働者が負けるケースの3つ目は、会社から説得的な主張や証拠ができてきた場合です。
あなたの主張に対して、会社側から説得的な主張や反論がされれば、あなたが適切な主張をしていたとしても、請求は認められないことがあります。
最終的な評価をするのは裁判所であり、過去の事実関係は変えることはできない以上、あなた自身が適切な主張をして、十分な証拠を出しても、負けてしまうことはあるのです。
労働審判で負けた労働者のリスクについては、労働者の取る行動によっても変わってきます。
労働審判は訴訟の前段階の手続きに過ぎませんので、労働審判で負けたとしても、それによって直ちに手続きが終わるわけではありません。
労働審判で負けた場合の労働者のリスクとしては、以下の3つです。

それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。
労働審判で負けた労働者のリスクの1つ目は、訴訟に進行した場合、訴訟移行後の裁判官の心証が悪くなってしまう可能性があることです。
労働審判委員会から審判を下された場合には、審判には異議を出すことができます。
例えば、請求を棄却するとの労働審判を出されたとしても、労働者がその審判に異議を出せば、審判は確定せずに通常の訴訟に移ることになるのです。
ただし、訴訟に移行した後については、労働審判の結果は訴訟移行後の裁判官も見ることになります。
請求を棄却するとの審判が出されていた場合には、労働者の請求は労働審判では認められていないという先入観を与えてしまう可能性があります。
また、訴訟移行後も、審判の内容を前提に裁判官から和解の試みをされることが多く、請求が棄却するとの審判がされていると労働者に不利な内容での和解を勧められがちです。
労働審判で負けた労働者のリスクの2つ目は、譲歩して調停に応じることになり、十分な支払いを受けられないというリスクです。
労働審判委員会は、労働者の請求を認めないとの心証の場合には、会社に対して請求が認められてしまう可能性が高いとの説得はしてくれません。
その結果、会社側は、中々譲歩に応じず、解決金の支払いに消極的な態度を示す傾向にあります。
これに対して、労働審判委員会は、労働者には、請求棄却との心証で、訴訟でも請求は認められない可能性が高いため、少ない金額でも和解に応じた方が良いと説得してきます。
そうなると、労働者が譲歩して調停に応じざるを得ない状況になり、十分な支払いを受けることが難しくなってしまうのです。
労働審判で負けた労働者のリスクの3つ目は、申立を取り下げることになり、労力や費用が無駄になるリスクです。
明らかに請求が認められないような場合には、会社側が1円たりとも支払いに応じることができないとの姿勢を示すことがあります。
このような事案では、裁判所も、会社側の説得は難しいとして、労働者側に対して、取り下げを勧告するようなことがあります。
労働審判の取り下げをした場合には、申立に要した労力は無駄になってしまいますし、収入印紙代や弁護士に払った着手金なども無駄になってしまいます。
労働審判の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判の費用については、以下の動画でも詳しく解説しています。
会社は、労働審判で労働者が負けた場合であっても、そのこと自体を理由として、労働者に対して、損害賠償を請求することは難しいです。
労働者には、裁判を受ける権利があり、裁判所に自分の請求を審理してもらう権利があるためです。
仮に労働者が負けた場合には、労働者に対して、損害賠償を請求できるということになれば、労働審判の申し立てを行うことが委縮してしまいかねません。
ただし、労働者が、事実や法律の根拠を欠くことを知りながら、会社への報復や嫌がらせなどの目的で申し立てた場合には、例外的に違法となる可能性もないとはいえません。
労働審判の申し立てを行う前に、弁護士にこのような請求が認められる余地があるのかということを相談しておくといいでしょう。
裁判を申し立てること自体が違法となるスラップ訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判で労働者が負けないためには、十分な準備と労働審判での適切な対応が必要になります。
説得的な主張や証拠により、労働審判委員会にあなたの請求を認めてもらう必要があるためです。
具体的には、労働審判で労働者が負けないための対策としては、以下の4つです。

それでは、これらの対策について順番に説明していきます。
労働審判で労働者が負けないための対策の1つ目は、弁護士に相談することです。
労働審判で負けないためには、法的な見通しに基づいて、適切な方針を立てることが大切です。
そのため、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
ただし、労働審判については、通常の訴訟手続とは異なりますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働事件をたくさん集まっていて、労働審判に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
労働審判で労働者が負けないための対策の2つ目は、十分な証拠を集めることです。
先ほども説明したように、会社側と主張が食い違っている場合には、証拠に基づき事実が認定されることになります。
あなたが正しい事実を裁判所に信じてもらうためには、可能な限り証拠を集めておくことが重要です。
請求する内容や事案に応じて、集めておくべき証拠も変わってきます。どのような証拠を集めておけばいいのか早めに弁護士によく相談しましょう。
労働審判で労働者が負けないための対策の3つ目は、必要な主張や反論を行うことです。
労働審判は全三回の期日で審理することになり、主張や証拠の提出は第2回の期日までに行う必要があるとされています。
答弁書が提出されるのは、通常、第1回期日の1週間程度前です。
第1回期日当日には、期日が始まる直前に労働審判委員会は事前評議を行うことになり、この評議によりおおよその心証を形成されてしまうこともあります。
答弁書では、労働者が申立段階では想定していなかった主張がされることも少なくありません。
このような場合に、労働者が答弁書に十分な反論をせずに第1回期日を迎えると、労働者側には反論はないものと見られてしまうこともあります。
そのため、会社側から答弁書が提出された際に、主張を補充する必要があれば、補充書面の提出も検討した方が良いのです。
労働審判で労働者が負けないための対策の4つ目は、労働審判委員会の話をよく聞くことです。
労働審判において、労働者の請求が認められるかどうかを判断するのは、労働審判委員会であるためです。
労働審判委員会から心証を開示される中で、どのような点を重視しているのかなどを聞いてみましょう。
第1回期日で心証を開示された後であっても、労働審判委員会の話を踏まえて主張を補充することで、第2回期日以降に心証が変わることがあります。
また、労働審判委員会の話を踏まえて、訴訟になった際のリスクが高いと感じた場合は、譲歩して調停に応じることで、請求が全く認められない結論を避けることができます。
そのため、労働審判委員会の話をよく聞くことで、労働審判で負けた際のリスクを回避できることがあるのです。
労働審判に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、労働審判で負けた労働者はどうなるかについて、3つのリスクと簡単な対策を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が労働審判を申し立てたいと考えているものの負けたらどうなってしまうのか不安に感じている労働者の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。