!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/08/21
不当解雇

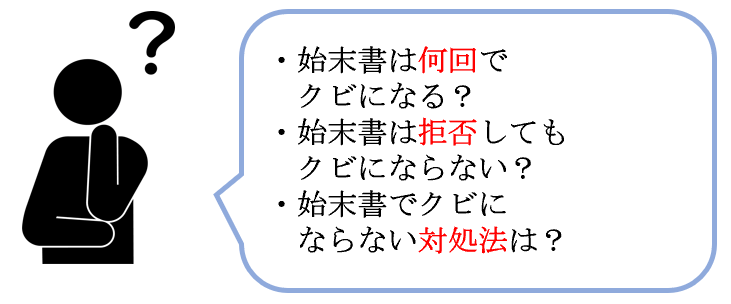
会社から始末書を書くように求められ、クビになってしまわないか不安に感じていませんか?
始末書へ記載すると、その内容が書面に残ってしまうことになりますので、自分に不利になってしまうのではないか心配ですよね。
始末書については、何回でクビになるなどの決まりはありません。
始末書を拒否しても、通常、それ自体を理由にクビにすることはできません。
始末書の記載内容によっては、今後クビにされた際に労働者に不利な証拠とされてしまうことがあります。
始末書の提出を求められても、会社に言われるままに記載するのではなく、冷静かつ適切に対処していくようにしましょう。
実は、会社から始末書を記載するように求められた際に誤った対処をしてしまうことによって、解雇の証拠とされてしまう事例が後を絶ちません。
私が相談を受ける中でも、すでに、十分に内容を検討しないまま大量の始末書を書いてしまっていて、もう少し早く相談していただきたかったと感じることが少なからずあります。
この記事をとおして、始末書がクビとの関係でどのように見られるのかということを多くの労働者の方に伝えることが出来れば幸いです。
今回は、始末書は何回でクビになるという決まりがあるのかを説明したうえで、解雇されないための対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
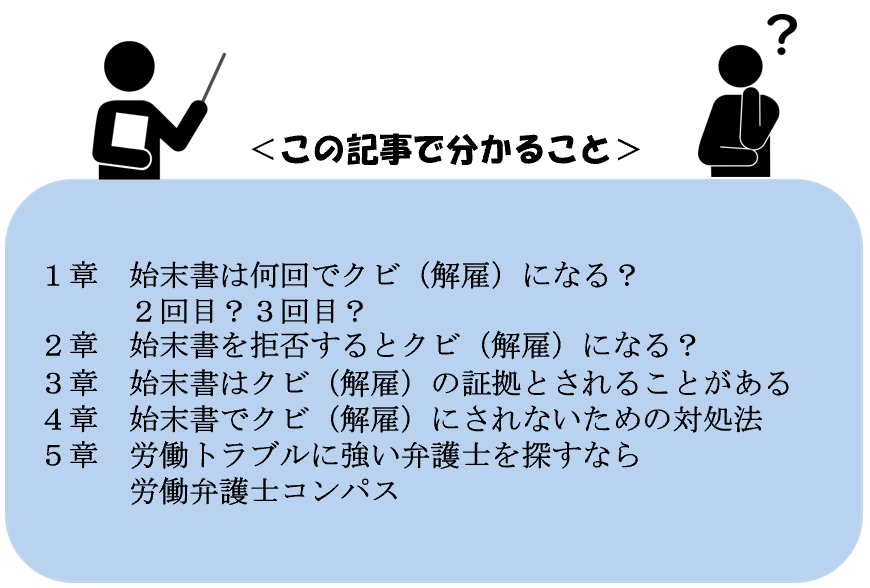
この記事を読めば、始末書を記載するように求められた際に、クビにならないようにするためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
始末書とクビについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
になる?.png)
始末書については、何回でクビになるなどの決まりはありません。
始末書というのは、反省していることを示して、再発をしないことを誓約する文書のことです。
始末書は、2回目や3回目になるとクビになるということを聞いたことがある人があるいるかもしれませんが、そのようなルールにはなっていないのです。
例えば、就業規則の解雇事由に始末書を2回提出したこと等の記載をしていたとしても、始末書を2回提出したこと自体を理由に解雇することは難しいでしょう。
また、始末書の末尾に再度同じことを繰り返した場合には、クビになっても異議はありませんなどと記載したとしても、その記載自体から解雇することは難しいでしょう。
ただし、繰り返し始末書を提出していることは、解雇の有効性を基礎づける事情の一つとなることがあります。
問題行動を何度も繰り返していて、始末書を提出しても改善しないという場合には、改善の余地がないと評価される事情となるためです。
になる?.png)
始末書を拒否しても、通常、それ自体を理由にクビにすることはできません。
労働者には、思想良心の自由があり、反省の意思を強要することはできないためです。
労働者が始末書の提出を拒否したとしても、業務命令違反などとして再度懲戒処分することはできないとされる傾向にあります。
例えば、国際航業事件では、労使関係においても個人の意思は最大限に尊重されるべきであるところ、始末書の提出命令は、それを業務上の指示命令としても、その拒否に対して懲戒処分をもって望むことは相当でないと判示されています。
(参考:大阪地判昭50.7.17[国際航業事件])
ただし、始末書を拒否したこと自体を理由にクビにはできないとしても、労働者が問題行動を起こしたことに加えて、改善の意欲がないことを理由に解雇されるリスクはあります。
そのため、始末書を拒否する方法や拒否する理由については、十分に検討したうえで、不利にならないよう慎重に対応する必要があります。
の証拠とされることがある.png)
始末書の記載内容によっては、今後クビにされた際に労働者に不利な証拠とされてしまうことがあります。
始末書自体に労働者が起こした問題行動の内容が記載されていたり、それが労働者の落ち度である旨が記載されていたりすることが多いためです。
会社から記載を求められる内容は、正確な事実関係よりも労働者に不利であったり、労働者に有利な経緯を無視したりしたものであることが多くなっています。
労働者自身がこのような始末書を記載してしまうと、後から、正確な事実関係を反論したり、労働者に有利な経緯等を反論したりすることは簡単ではありません。
そのため、始末書はクビの証拠とされてしまい、安易に会社に言う通りに記載してしまうと反論が難しくなってしまうことも多いのです。
始末書の提出を求められても、会社に言われるままに記載するのではなく、冷静かつ適切に対処していくようにしましょう。
これまでに説明したように、会社の言うままに記載したり、安易に拒否したりしてしまうと、クビにする際の証拠とされてしまうことがあるためです。
具体的には、始末書の提出を求められた際に、クビにされないためには以下の方法により対処していくといいでしょう。
にされないための対処法4つ.png)
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
始末書でクビにされないための対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
解雇の有効性やその証拠については法的な事項であり、どのような記載や対応が不利になってしまうかについては、法律の専門家の弁護士に相談するべきです。
解雇事件を多く取り扱っている弁護士であれば、裁判を見据えてどのような対応をするのが適切かを助言することができるはずです。
ただし、始末書への対応については、まだ紛争が発生していないため、初回無料相談の対象としていない事務所が多いでしょう。
もし相談を断られてしまった場合には有料相談であれば可能か確認してみたり、元々有料相談を行っている事務所に問い合わせてみたりすることがおすすめです。
始末書でクビにされないための対処法の2つ目は、事実と異なる記載をしないことです。
始末書は労働者自身が記載するものであり、会社から言われてやむを得ずこのように記載した等の言い分は簡単には認められません。
一度、始末書に不利な記載をしてしまうと、実はこの記載は事実と異なります説明することは難しくなってしまうのです。
例えば、あなたが指示された業務を行っていなかったという理由で始末書を記載するように求められたとしましょう。
しかし、実際には、あなたに対して明確な業務の指示は行われていなかったため、その業務をしていなかったという場合を想定します。
このような場合に、「指示された業務を行っておらず申し訳ございませんでした」と記載してしまうと、後から、業務指示がなかったとの反論をすることが難しくなることがあります。
そのため、細かい表現であっても、不利になってしまうことがありますので、不正確な記載はしないようにしましょう。
始末書でクビにされないための対処法の3つ目は、自分の言い分を弁明し証拠化しておくことです。
会社側から問題行動等を指摘される場合であっても、多くの場合には労働者に言い分があり、その経緯等からは労働者の落ち度とは言えないようなこともよくあります。
このような場合に、何も弁明せずに始末書を書き、反省の意を述べてしまうと、あなた自身も、この件については自分に落ち度があると認めていたのではないか等の指摘をされることがあります。
そのため、自分に落ち度がなかった経緯等があるのであれば、メールやチャットで弁明したうえで、証拠化しておくといいでしょう。
ただし、一度、メールやチャットで弁明を送ってしまうと、裁判になった際にそれとは異なる事実関係を主張することが難しくなりますので、慎重に検討したうえで送りましょう。
始末書でクビにされないための対処法の4つ目は、拒否する際は理由と改善の意思を示しておくことです。
何も理由をつけずに始末書の提出を拒否してしまうと、改善の意思がなかったとして、解雇する際の事情の一つとされることがあります。
なので、始末書を拒否する際には、なぜ拒否するのかという理由を示した方が良いでしょう。
例えば、会社側が指摘している事実関係が自身の認識と異なるため、始末書を記載する前に認識のすり合わせをさせてほしい等のお願いをする場合などがあります。
また、改善の意思がないとの指摘を避けるため、もし自分に至らない点があったのであれば改善する意思がある旨を伝えておくといいでしょう。
労働トラブルに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、始末書は何回でクビになるという決まりがあるのかを説明したうえで、解雇されないための対処法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が始末書を記載するように求められてクビにならないか不安に感じている労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。