!.png)
2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/08/21
労働災害

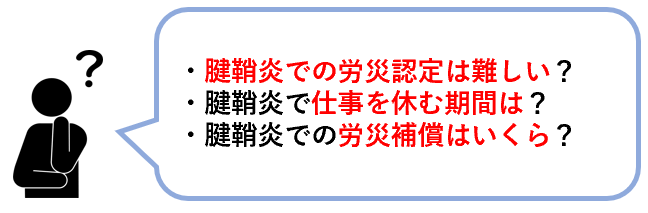
仕事をしていて腱鞘炎になってしまい困っていませんか?
腱鞘炎になると仕事にも支障が出てしまいますので補償を受けたいと考えることは自然なことですよね。
腱鞘炎について、労災認定を受けることは容易ではなく難しいことも多いです。
腱鞘炎の労災認定されるためには、いくつかの条件が必要となります。
腱鞘炎で仕事を休む必要がある場合には、その期間は3週間~6週間程度でしょう。
腱鞘炎での労災補償としては、医療費や薬品費、休業補償などがあります。
腱鞘炎で労災申請を受ける際には、厚生労働省のホームページで様式をダウンロードしたうえで必要事項を記載することになります。
ただし、労災保険のみでは補償されない損害については、会社に対して安全配慮義務違反等を理由に賠償請求をすることが考えられます。
実は、仕事で腱鞘炎になってしまう方が多いですが、日常生活でも発症しやすい症状になりますので、適切な補償を受けるためにはポイントを押さえて、しっかりと準備することが不可欠です。
この記事をとおして、仕事中に腱鞘炎になってしまった方に労災について必要な知識を伝えていくことができれば幸いです。
今回は、腱鞘炎の労災認定の難しさについて説明したうえで、仕事を休む期間や補償の内容について解説していきます。
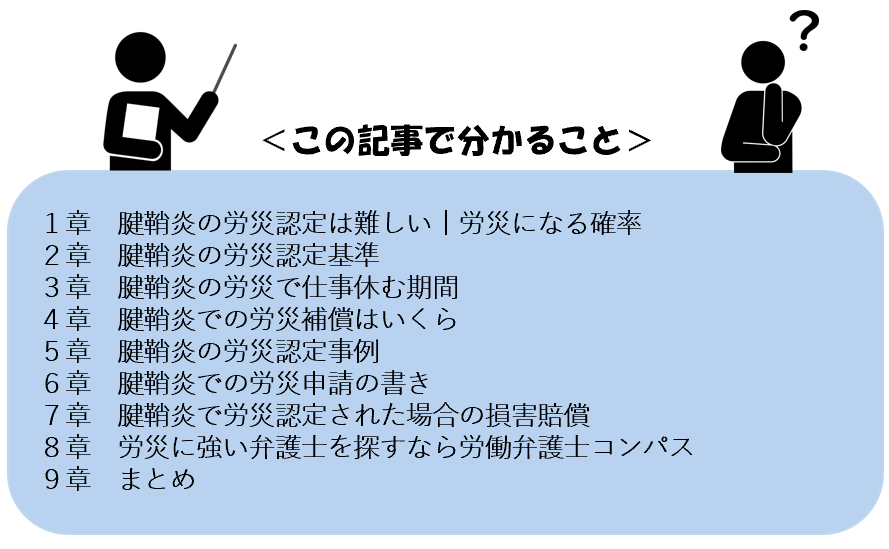
この記事を読めば、仕事中に腱鞘炎になってしまった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す

腱鞘炎について、労災認定を受けることは容易ではなく難しいことも多いです。
腱鞘炎は、日常生活でも発症しやすい症状になりますので、業務により発症したことを証明することが容易ではないためです。
例えば、受付業務や経理など、主な業務がデスクワーク中心で、一見すると手首に強い負担がかかっているように見えない職種でも、実際には日々の伝票整理や帳票の処理、電話応対での書き作業が積み重なり、腱鞘炎を引き起こすことがあります。
しかし、こうした「軽度な動作の積み重ね」が原因と考えられるケースは、業務との直接的な因果関係が見えづらく、労基署に「家事や趣味の影響ではないか?」と判断されてしまうこともあります。
さらに、「同じ業務をしている他の従業員が発症していない」という理由で、個人の体質や年齢によるものと片付けられてしまうリスクもあります。
このように、腱鞘炎で労災認定されるには、日常的に行っていた具体的な作業や作業時間の記録、痛みの発生時期などを詳しく整理し、業務による負荷であることを丁寧に証明していくことが求められます。
どんな作業を、どれくらいの時間・頻度で行っていたのか、発症時期や経過などを、できる限り具体的に記録・説明していく必要があります。
腱鞘炎で労災と認定されるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
それでは、これらの条件について順番に説明していきます。
腱鞘炎の労災認定基準の1つ目は、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したことです。
「上肢等」とは、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指をいいます。
「相当期間従事した」とは、原則として6か月以上従事した場合を言います。
例えば、上肢等に負担のかかる作業としては以下のようなものがあります。
腱鞘炎の労災認定基準の2つ目は、発症前に過重な業務に就労したことです。
発症直前3か月間に、上肢等に負担のかかる作業を次のような状況で行ったこと場合をいいます。
腱鞘炎の労災認定基準の3つ目は、過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められることです。
つまり、業務内容と発症までの時間的な流れや症状の現れ方が、医学的な観点から見て不自然でないことが求められます。
例えば、ある業務に就いてから急に痛みが出た、もしくは負荷の高い作業が始まってから徐々に痛みが増してきたというような場合です。
一方で、長期間同じ業務に就いていたにもかかわらず、発症が不自然に遅れていたり、私生活の影響が強く疑われるような場合には、この条件を満たさないと判断されることもあります。
業務と症状の関係について、医師の意見書や診断書で医学的な説明があると、認定されやすくなります。
腱鞘炎の労災で仕事を休む期間は、個人差がありますが、一般的には3週間から6週間程度とされています。
ただし、腱鞘炎になったからといって必ずしも、仕事を休む必要まではないこともあります。
職場での配置転換や業務内容の変更などにより、手首への負担を軽減した形で働き続けることが可能なことも多いためです。
例えば、入力作業を一時的に減らしたり、反復動作の少ない作業に変えてもらうことで対応できるケースもあります。
こうした対応が難しい場合や、痛みが強く業務に支障が出る場合には、医師の指示に従って一定期間の休職が必要となります。
医師からの診断書をもとに、治療とリハビリに専念することで、再発や慢性化を防ぐことができ、結果的に早期の職場復帰につながります。
リハビリや治療を行いながら徐々に職場復帰を目指すケースも多く、会社や産業医と連携しながら、体調に応じた復職プランを立てるようにしましょう。
腱鞘炎で労災と認定された場合には、いくつかの補償を受けることができる可能性があります。
例えば、腱鞘炎が労災とされた場合に受けることができる可能性のある補償としては以下のものがあります。
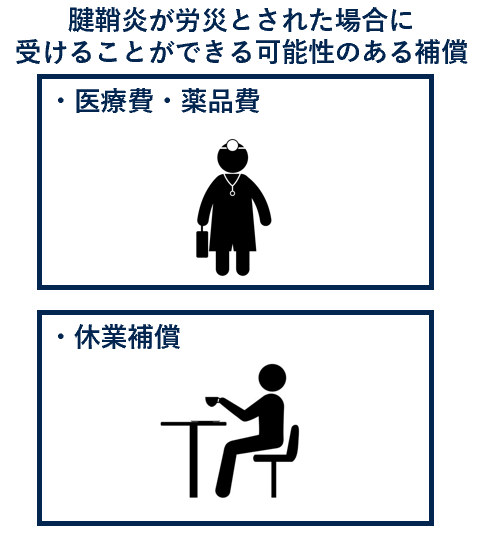
それでは、これらの補償について順番に説明していきます。
腱鞘炎が労災と認定された場合の補償の1つ目は、医療費や薬品費です。
診察費用や検査費用、レントゲン費用、手術費用、処方された薬代などがかかることがあります。
労災病院で治療を受ける際には、無料で治療を受けることができ、労災保険から直接労災病院に支払いが行われることになります。
労災病院以外で治療を受ける際には、一度自分で立て替えた後に、労災保険から返金してもらうことになります。
具体的には、労災と医療費については、以下の記事で詳しく解説しています。
腱鞘炎が労災と認定された場合の補償の2つ目は、休業補償です。
配置転換や業務の変更、負担を軽減した働き方での対応が難しい場合には、仕事を休まざるを得ないことがあります。
このような場合には、休業補償により、給付基礎日額(事故直前の3ヶ月の平均給与)の約80%が労災保険により補償されます。
内訳は、休業補償給付60%、休業特別支給金20%となります。
腱鞘炎や類似の上肢障害で労災認定された事例を紹介します。
これらの事例は、どのような業務実態が「過重な業務」と判断されるかを理解するうえで参考になります。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。
Aさんは入社から2年間、パソコンで顧客情報などを入力する業務に従事していました。ある日、肘から指先にかけてしびれや痛みを感じ、病院で「腱鞘炎」と診断されました。
労働基準監督署が調査した結果、Aさんの発症直前3か月間の作業量は、同様の業務を行っている同僚の1時間あたり約80件に対して、Aさんは1時間あたり約100件。つまり、他の労働者と比べて10%以上多い業務量が続いていたと判断されました。
そのため、通常より明らかに負荷の大きい作業に従事していたとされ、腱鞘炎の発症との関係性が認められた結果、労災が認定されました。
Bさんは作業療法士として5年間、患者のリハビリを補助する業務を担当していました。右肘に強い痛みを感じるようになり、腕の曲げ伸ばしが困難になったため医療機関を受診したところ、「上腕骨内上顆炎」と診断されました。
調査の結果、同僚の退職により業務負担が急激に増え、それまで1日平均12人の患者を担当していたところ、直前3か月間は1日あたり20人前後の患者を対応する日が毎月10日以上発生していました。
このような業務量の増加が「過重な業務」と判断され、疾患との因果関係も医学的に妥当とされて、労災として補償される結果となりました。
腱鞘炎で労災申請を受ける際には、厚生労働省のホームページで様式をダウンロードしたうえで必要事項を記載することになります。
通常、医療費や薬品費については様式第7号、休業補償については様式第8号を使います。
必要事項を記入したら、事業主と医師に証明をお願いします。
会社から証明を拒否されてしまう場合もあり、この場合には労基署に事業主の証明を得られなかった経緯を説明する必要があるので、書面などで証明をお願いするといいでしょう。
その他、労災の認定をしてもらうのに必要な資料などを添付して、労基署に提出することになります。
腱鞘炎で労災認定された場合には、安全配慮義務違反などを理由として、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
労災保険で補償されるのは損害の一部のみにすぎず、労災保険のみでは労働者の損害の補償としては不十分であるためです。
例えば、休業損害について、労災では休業補償給付は給付基礎日額の60%にとどまっていますので、差額を会社に請求できる可能性があります。
また、慰謝料については、労災保険では補償されませんので、精神的苦痛に対する補償をしてほしい場合には、会社に損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求については専門的となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
安全配慮義務違反を理由とする損害賠償については、以下の記事で詳しく解説しています。
労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。


労働弁護士コンパスで
労働問題に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、腱鞘炎の労災認定の難しさについて説明したうえで、仕事を休む期間や補償の内容について解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が仕事をしていて腱鞘炎になってしまい労災を受けることができないか困っている労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

尾形達彦
尾形総合法律事務所
福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

豊田雄一郎
フリューゲル法律事務所
東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室
詳細はこちら

小竹真喜
黒木法律事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階
詳細はこちら
人気記事
!.png)
2025年3月8日
労働一般
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日
不当解雇
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日
ハラスメント
逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。