
2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。
2025/11/25
法律手続

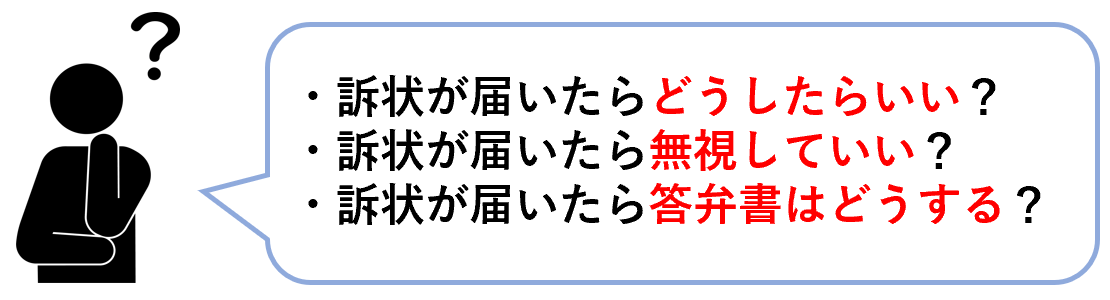
裁判所から訴状が届いてしまいどうすればいいのか悩んでいませんか?
いきなり訴状が届いてパニックになってしまっているかたもいますよね。
訴状が届いたら、答弁書の提出を求められ、第1回期日への呼び出しをされることになります。
封を切らずに無視すると、あなたにとって不利な判決を出されてしまい、一方的に財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
もし、訴状が届いた場合には、事例ごとに気を付けてほしいポイントがあります。
請求を争いたい場合には、まずは「原告の請求を棄却する」との記載をした答弁書を提出しておくのが通常です。
訴状が届いた後でも和解をすることはできますが、争いがある事案では双方がある程度主張立証を尽くした段階で裁判所から和解の話をされることが多いです。
訴状が届いたら、あなた自身の権利や利益を守るためにも、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。
あなたに合った弁護士を探すことが良い解決をするための近道です
実は、訴状が届いた後にどのような対応をしていくかによって、良くも悪くも結果は大きく変わってきます。
この記事をとおして、訴状が届いてしまい不安に感じている方々に是非知っておいていただきたいことを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、訴状が届いたらどうしたらいいのかについて、封を切らずに無視はNGであることを説明したうえで、よくある疑問や簡単な対処手順を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
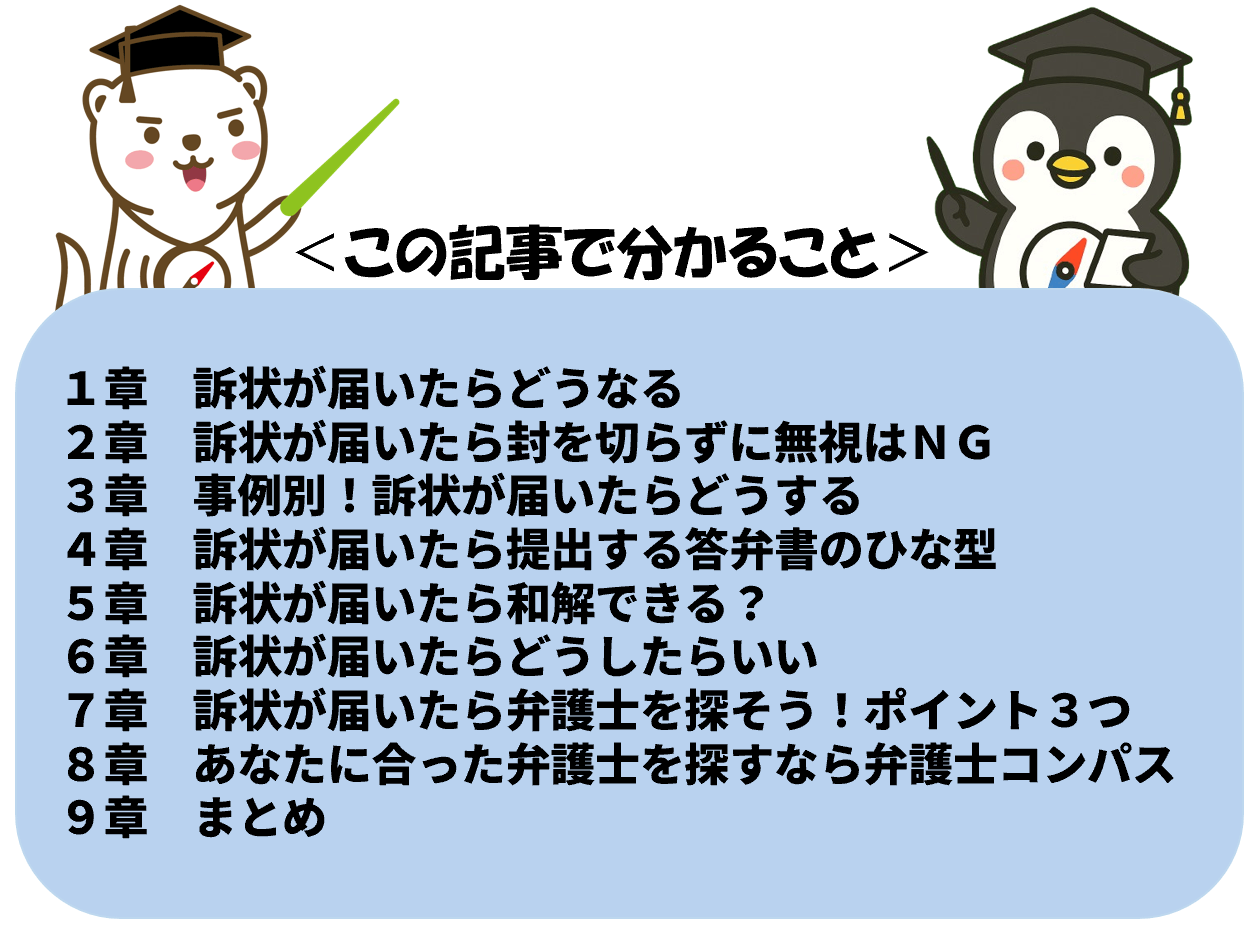
この記事を読めば、裁判所から訴状が届いたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す

訴状が届いたら、答弁書の提出を求められ、第1回期日への呼び出しをされることになります。
訴状が送達されることで裁判の始まり、訴訟が正式に係属することになるためです。
例えば、訴状が入っている封筒の中には呼出状が入っているのが通常で、答弁書の提出や第1回期日についての説明が記載されています。
第1回期日の後は、1~2か月に1回程度の頻度で期日が入り、双方が主張と立証を尽くしていき、判決を目指していくことになります。
期日の中では、提出された答弁書や証拠をもとに議論が整理され、必要に応じて追加の資料提出や証人尋問が行われることもあります。
このように、訴状が届くことにより裁判は始まり、訴訟が係属して判決に向けた流れが動き出すことになります。

訴状が届いたのに封を切らずに無視するのは避けるべきです。
答弁書を出さずに第1回期日に欠席してしまうと、「欠席判決」といってそのまま原告の請求が認められてしまう可能性があるためです。
例えば、300万円の貸金の返還を求める訴訟を提起されたとしましょう。
これについて実際には既に消滅時効が完成しているので、あなたは時効を援用することで、支払いを免れたいと考えていたとします。
しかし、訴状を無視して答弁書を出さずに第1回期日に欠席すると、300万円の支払いを命じる判決が出されてしまい、財産を差し押さえられてしまう可能性があるのです。
このように、訴状を受け取った時点で裁判は動き出しているため、無視しても状況は良くならず、むしろ不利になるだけです。
訴状が届いたらよく中身を確認し、期限までに対応するようにしましょう。
訴状が届いたときの対応は、請求の内容や原因によって変わります。
自分の事案に応じた対応を知っておくことで適切に対応しやすくなります。
例えば、訴状が届いたらどうするか知っておいていただきたいことを事例別に整理すると以下のとおりです。
それでは、これらのケースごとに順番に見ていきましょう。
借金を理由に訴状が届いた場合には、返済義務の有無や金額を確認することが最初の一歩です。
なぜなら、すでに返済が終わっているのに誤って請求されている場合や、時効が成立している場合もあるからです。
例えば、最後に返済してから5年以上経過している消費者金融からの請求では、消滅時効を主張できるケースもあります。
また、本当に返済できない状況であれば、自己破産や任意整理といった債務整理を検討することも現実的な選択肢です。
このように、借金で訴状が届いたら、返済記録や時効の有無を確認し、場合によっては債務整理も視野に入れて冷静に判断することが大切です。
不貞行為を理由に訴状が届いた場合には、まず不貞の有無と慰謝料額が適正かどうかを確認する必要があります。
なぜなら、事実がないのに請求されている場合もあれば、不貞の事実があっても慰謝料の額が高すぎる場合もあるからです。
例えば、単なる友人関係であるにもかかわらず不貞と決めつけられて訴えられている場合には、やり取りの内容や会っていた状況をもとに反論することができます。
一方で、不貞の事実がある場合でも、慰謝料が数百万円と高額であれば、裁判例の相場を踏まえて減額を求める余地があります。
このように、不貞を理由にした訴状では、事実関係と金額のそれぞれを検討し、相手の請求が妥当かを冷静に見極めることが重要です。
交通事故で損害賠償を請求するとの訴状が届いた場合には、まず任意保険会社に報告することが重要です。
何も報告せずに敗訴したり、和解したりしてしまうと、保険により対応してもらえないことがあるためです。
例えば、事故の過失割合に争いがある場合や、治療費・休業損害の金額が大きい場合でも、保険会社が代理人弁護士をつけて対応してくれることがあります。
このように、交通事故で訴状が届いたら、まずは任意保険会社へ報告し、どのように対応すべきかを確認することが解決への近道です。
少額訴訟で訴状が届いた場合には、通常訴訟に移行すべきかどうかを検討する必要があります。
なぜなら、少額訴訟は60万円以下の請求を対象に原則1回で判決が出る仕組みであり、十分な準備をする時間が限られているからです。
例えば、証拠が多く整理に時間がかかる場合や、相手の請求額に大きな争いがある場合には、通常訴訟へ移行した方が丁寧に主張立証できる可能性があります。
逆に、シンプルな金銭トラブルであれば少額訴訟で迅速に解決することも選択肢になります。
このように、少額訴訟の訴状が届いたら、事案の複雑さに応じて通常訴訟への移行を検討し、どの手続が自分にとって有利かを見極めることが重要です。
訴状が届いたら提出する答弁書のひな型としてよくあるのは、以下のとおりです。
ここでは結論を明確に記載します。
例えば「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」といった形で、裁判所にどのような判決を求めるのかを示します。
原告が主張する事実について「認める」「否認する」「不知」を明確に記載します。
例えば「借金をした事実は認めるが、その余は否認する」といった形で、一つ一つ整理して答えることが大切です。
ただし、答弁書の提出期限に間に合わないような場合には、「おって主張する」とだけ記載しておくことが多いです。
自分の立場や考えをまとめる部分です。
例えば「すでに返済は終わっている」「消滅時効を援用する」といった、自分の主張を丁寧に記載します。
ただし、答弁書の提出期限に間に合わないような場合には、「おって主張する」とだけ記載しておくことが多いです。
裁判所や相手方からの書類をどこに送ってもらうかを指定します。
住所や電話番号、FAX番号などを記載しておくことで、今後のやり取りがスムーズになります。
第1回期日に出頭しない場合には、「本答弁書をもって陳述を擬制されたい」などの記載をしておくことが多いです。
答弁書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
訴状が届いた後でも、裁判の中で和解することは可能です。
なぜなら、訴訟上の和解という制度があり、裁判所からも適宜和解の意向が確認されることが多いためです。
裁判では、双方が主張や証拠をある程度出し終えた段階で、裁判官から「和解による解決を検討してはどうか」と提案されることがあります。
例えば、裁判官が「主張も出そろってきたので、次回期日で個別に今後の進行についてお話させてください。」などと言われることがあります。
和解するか、尋問など判決に向けて手続きを進めていくか聞きたいという意味で使われることが多い言い回しです。
裁判官から現状での心証を示されたうえで、手続きを進めた場合のリスクなどを伝えられて、和解してはどうかと促されます。
このように、訴状が届いたからといって必ず判決まで行くわけではなく、裁判の途中で和解して終了することも少なくありません。
自分にとって不利な判決を避けたい場合や、早くトラブルを解決したい場合には、和解の可能性も視野に入れて検討することが大切です。
ただし、事実関係に争いがあったり、法的な争点があったりする事案では、訴訟提起後すぐには和解の話にはなりにくいです。
裁判所も、お互いの主張や証拠が十分出ていない段階だと、心証を形成できておらずどのような和解が適切か判断できないためです。
訴状が届いたら、焦らず冷静に手順を踏んで対応していくことが大切です。
手続きを誤ると不利な判決につながる可能性がある一方で、正しく進めれば自分の権利を守ることができるからです。
対応の流れを理解しておけば、必要以上に不安にならず落ち着いて行動できます。
具体的には、訴状が届いたら以下の手順で対応していくといいでしょう。

それでは、これらの手順について順番に見ていきましょう。
まずは訴状をしっかり確認することが大切です。
訴状には「相手がどのような請求をしているのか」が具体的に書かれているからです。
何を請求されているかによって今後の対応も探すべき弁護士も変わってきます。
さらに、訴状と一緒に送られてくる呼出状には「答弁書の提出期限」や「第1回期日の日時」が記載されています。
このように、訴状の内容と期日の両方を確認しておくことで、対応方針を早めに整理し、次の行動に移りやすくなります。
呼出状については、以下の記事で詳しく解説しています。
訴状が届いたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
答弁書の提出期限が決められている一方で、一度答弁書を提出してしまうと記載した内容を後から撤回することは容易ではないためです。
例えば、証拠の出し方や答弁書の書き方などは専門的な知識や判断が求められるため、弁護士のサポートを受けるといいでしょう。
弁護士に依頼することで、答弁書の作成や期日の対応などを代わりに行ってもらうことができます。
期限までに答弁書を提出するようにしましょう。
答弁書を提出せず欠席してしまうと、そのまま原告の請求が認められてしまうリスクがあるためです。
例えば、請求内容を争う場合には、「原告の請求を棄却する」などの答弁を記載した答弁書を提出することが多いです。
答弁書を提出したら、第1回期日に出頭するか又は擬制陳述することになります。
陳述することで答弁書に記載された内容が被告の主張となるためです。
なお、第1回期日が終わったら、第2回期日の調整を行うことになり、事案に応じて裁判所から次回までにやってくることなどが指示されます。
訴状が届いたら、できるだけ早く自分に合った弁護士を探すことが大切です。
依頼する弁護士次第で対応方針は変わってきますし、結果も変わってくる可能性があります。
例えば、訴状が届いた際に弁護士を探すポイントは、以下の3つです。
それでは、これらのポイントについて順番に見ていきましょう。
弁護士を選ぶ際には、取り扱っている専門分野をよく確認しましょう。
同じ弁護士でも得意分野が異なり、労働問題に詳しい人もいれば、離婚や交通事故に強い人もいるからです。
例えば、不貞慰謝料で訴状が届いたのに企業案件ばかり扱う弁護士に依頼すると、最適な解決につながりにくい可能性があります。
このように、自分の事案に合った専門分野の弁護士を選ぶことが、納得のいく解決につながります。
依頼する前に、弁護士費用の仕組みを確認しておきましょう。
現在、弁護士報酬については自由化されており、事務所ごとに費用の体系が大きく違ってきます。
例えば、着手金の有無や報酬金の割合、日当の金額など事前によく確認しておくといいでしょう。
費用面をしっかり確認して納得したうえで契約することが大切です。
ただし、安い弁護士が必ずしも良いというわけではなく、経験や対応力も含めて総合的に判断することが重要です。
弁護士を選ぶ際には、1人だけでなく複数人に相談してみることをおすすめします。
弁護士によって説明の仕方や解決方針が異なり、自分に合う合わないがあるからです。
例えば、同じ事案でも「裁判で徹底的に争うべき」と言う弁護士もいれば、「和解で早期解決を目指すべき」と提案する弁護士もいます。
複数相談することで選択肢を広げ、信頼できる弁護士を選ぶことができるのです。
弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、訴状が届いたらどうしたらいいのかについて、封を切らずに無視はNGであることを説明したうえで、よくある疑問や簡単な対処手順を解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が裁判所から訴状が届いてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

鴨下香苗
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階
詳細はこちら

小藤貴幸
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

三部達也
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階
詳細はこちら
-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)
髙田晃央
髙田法律事務所
東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階
詳細はこちら
人気記事

2025年5月2日
法律一般
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日
法律手続
裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日
法律手続
債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。