
2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。
2025/11/25
法律手続

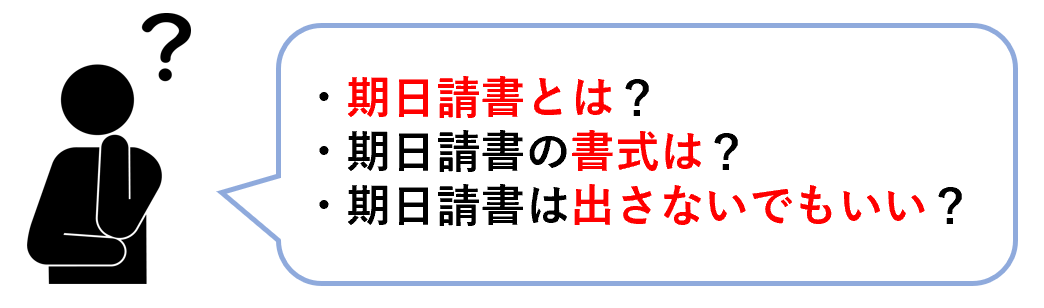
期日請書について知りたいと悩んでいませんか?
司法修習などでも期日請書について丁寧に教えられず、実務に出て、なんでこんなものを出さなければいけないのかと悩んでいる弁護士の先生もいるかもしれません。
あるいは、本人訴訟をしている方で期日請書をという言葉を目にして、どのようなものか気になっている方もいるでしょう。
期日請書とは、裁判所から期日の呼び出しを受け了承したことを届け出る書面のことです。
期日請書には、「頭書事件につき、第1回期日を令和●年●月●日午後●時●分との指定を受けましたので、お請けいたします。」などの記載をします。
期日請書の提出を求められるのは、「呼出状の送達」又は「出頭した者に対する期日の告知」以外の方法で、期日の呼び出しがされる場合です。
書記官から電話があり期日が指定された際にあわせて期日請書を提出してくださいと言われますので、このような指示があったら提出することになります。
私も、実務1年目の頃は、この期日請書に一体どのような意味があるのか、本当に提出しなければいけないのかと素朴な疑問を抱いたことがあります。
この記事をとおして、期日請書が実務上どのような意味をもっているのかということを分かりやすく整理して説明することができれば幸いです。
今回は、期日請書とは何かを説明したうえで、実務書式やひな形と簡単な書き方を弁護士が解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
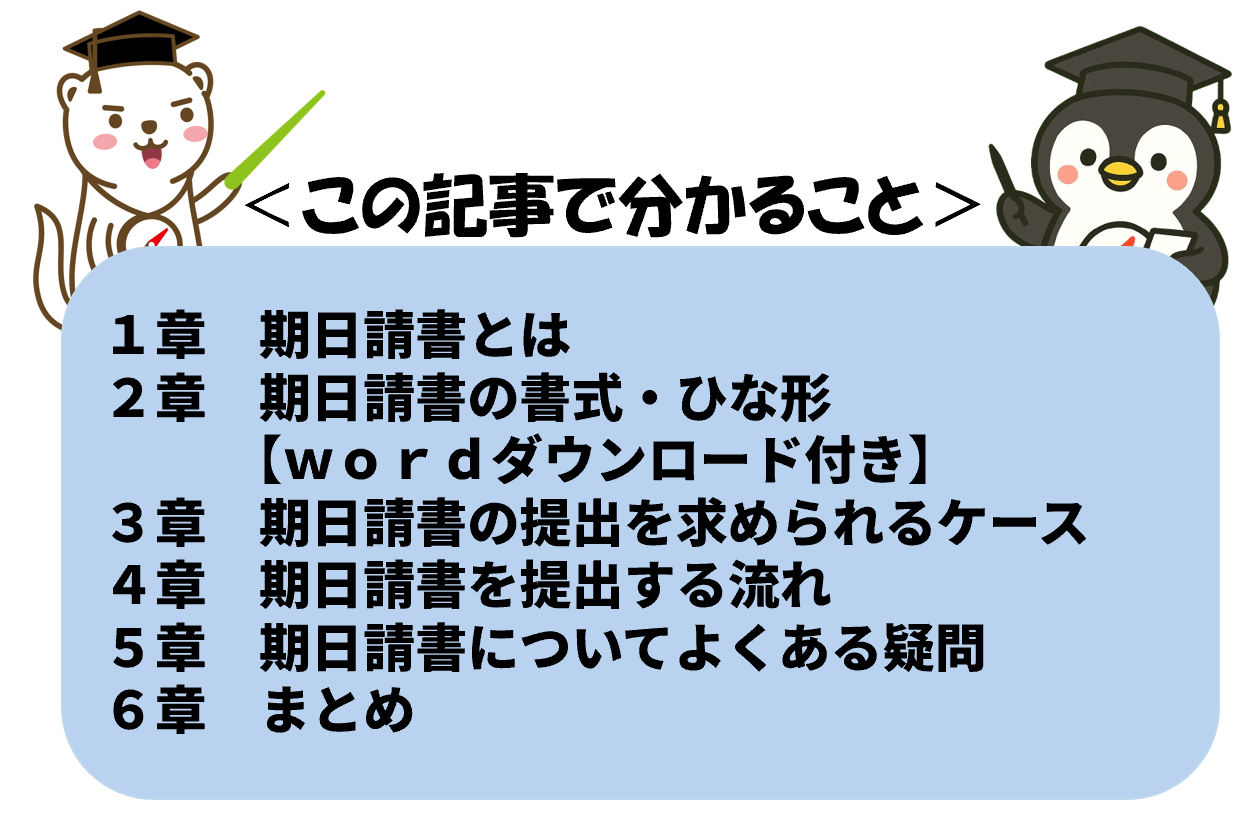
この記事を読めば、期日請書を提出してほしいと言われた際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す
期日請書とは、裁判所から期日の呼び出しを受けた際に提出する指定された期日を了承する書面のことです。
「きじつうけしょ」と読みます。
本来裁判所は、呼出状の送達、又は、出頭した者に対する期日の告知のいずれかの方法で期日の呼び出しを行います(民事訴訟法94条1項)。
期日請書は、呼出状の送達を省略して、書記官が電話で期日を指定した場合でも、当事者に期日付遵守の不利益を負わせることを可能にするものです(民事訴訟法94条2項)。
不利益とは、不明瞭な攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条2項)、欠席による擬制自白(民事訴訟法159条3項)などがあります。
期日を承諾したことを明確にしておきトラブルを防ぐという実質的な意味もあります。
本人訴訟の場合には呼出状が送付される傾向にあり、弁護士が代理人に付いている場合などに期日請書が用いられるのが通常です。
例えば、裁判所から事務所に電話があり、期日を指定されて、期日請書を提出してくださいと言われることになります。
このような指示があれば期日請書を提出することになります。
呼出状については、以下の記事で詳しく解説しています。
期日請書の書式は、以下のとおりです。
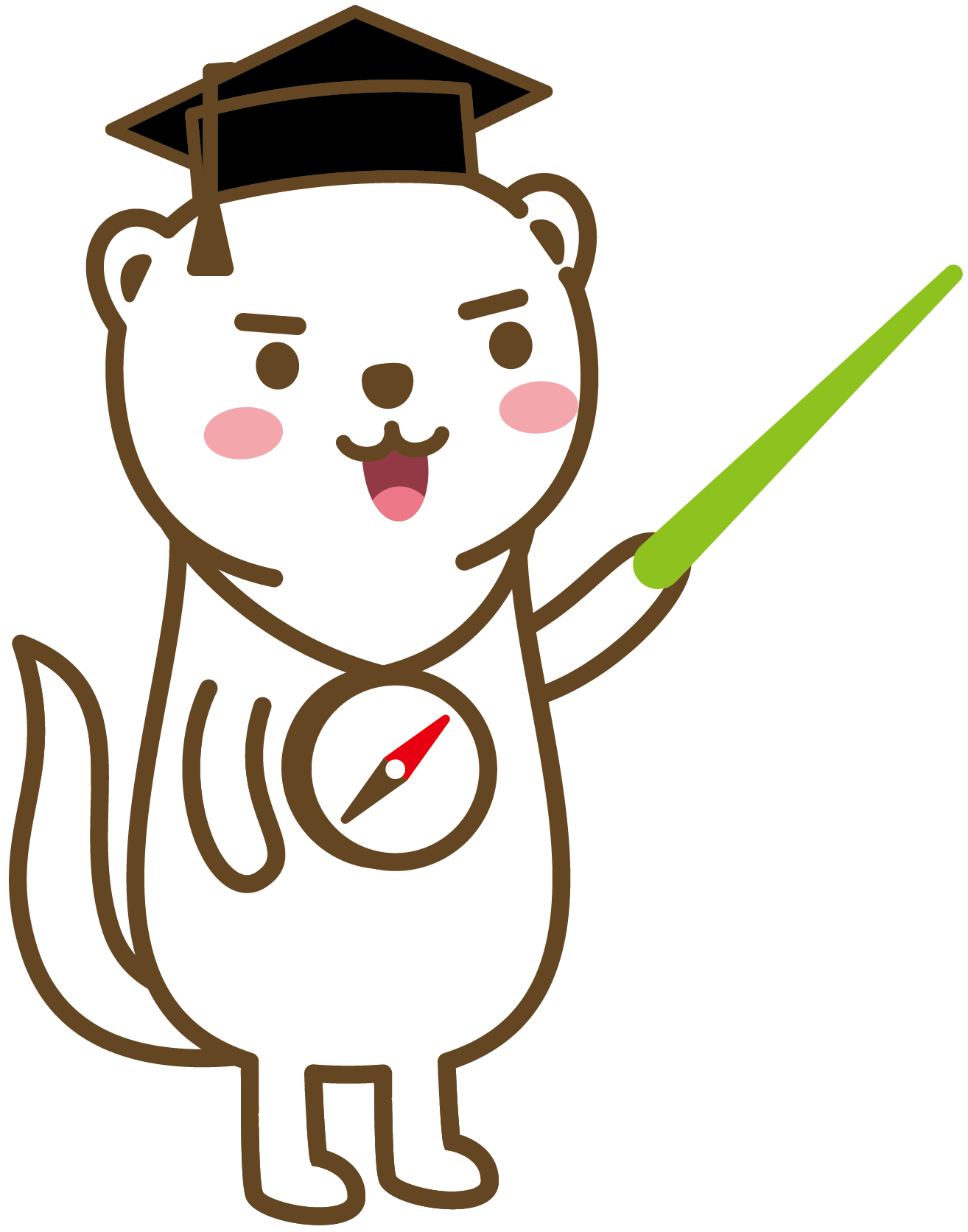
期日請書のサンプル
作成日はとくに決まりはないので提出する日を記載しておくといいでしょう。
原告代理人と被告代理人の記載を間違えないようにしましょう。
「口頭弁論期日」、「弁論準備手続期日」などの弁論期日の種類については、裁判所の書式には記載されていますが、とくに記載しなくても問題ありません。
以下に裁判所の参考書式のリンクをおいておきます。
口頭弁論期日請書|東京簡易裁判所.pdf
web会議の期日請書についても、上記のとおり送付して問題ありません。
web会議であることを明確にしたい場合には、「次回期日(web期日)」、「弁論準備手続期日(web期日)」などの記載にしておく方法があります。
第2回期日以降の期日請書については、「第1回期日」との部分を「次回期日」とすることが多いです。
調停の期日請書については、「原告」との部分を「申立人」、「被告」との部分を「相手方」とすることが多いです。
刑事事件の期日請書については、「原告代理人弁護士●●●●」の部分について、「弁護人●●●●」と記載します。
頭書(あたまがき)の部分についても、「原告」の記載は削除し、「被告」の部分は「被告人●●●●」と刑事事件に沿うように修正します。
期日請書の提出を求められるのは、「呼出状の送達」又は「出頭した者に対する期日の告知」以外の方法で、期日の呼び出しがされる場合です。
とくに、弁護士が代理人に就いている場合には、呼出状の送達に代えて、電話での期日指定と期日請書の提出による方法がとられることが多いです。
具体的には、期日請書の提出が求められるケースとしては、以下の3つがあります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
原告・申立人側で第1回期日が指定された場合には、期日請書の提出を求められるのが通常です。
被告側は、訴状と一緒に呼出状も送達されますので、期日が変更されない限りは、期日請書の提出は求められません。
これに対して、原告・申立人側に対しては、書記官から電話やFAXで日程調整の連絡がきます。そして、期日が決まったら書記官から電話があり伝えられることになります。
そのため、原告・申立人側は、第1回期日が指定された際には、期日請書の提出を求められます。
期日が変更された場合にも、期日請書の提出が求められます。
訴状送達後、被告側にも代理人弁護士が就いた場合には、第1回期日を取り消し、弁論準備手続期日に付したうえで、期日の日程を変更するということがよくあります。
このような場合には、原告側・被告側、それぞれに期日請書を提出するよう求められるのが通常です。
また、当事者から期日間に何らかの理由で、期日変更の上申所が提出されて、期日の再調整がされたような場合には、期日が変更されます。
体調不良や次回期日までに準備が間に合わないと言ったような場合が典型例です。
このような場合にも、原告側・被告側、それぞれに期日請書の提出を求められるのが通常です。
期日外で期日が指定された場合にも、期日請書の提出が求められます。
証人尋問期日などで、証人の出頭できる日程が不明であるため、次回期日を指定せず、期日後に次回期日の日程を調整することにしたような場合です。
裁判手続が休止され、再開の期日指定がされたような場合にも、期日外で新たに期日の指定がされることになります。
このような場合には、原告側・被告側、いずれも期日請書の提出を求められることになります。
期日請書を提出する流れは、以下のとおりです。
それでは、順番に説明していきます。
まず、書記官から法律事務所に電話があり、期日が決まったと伝えられます。
例えば、「次回期日は、令和●年●月●日午後●時●分からとなります。」と言われます。
次に、上記の電話の中で、期日を伝えられた後、そのまま書記官から期日請書の提出を求められることになります。
例えば、「期日請書の提出をお願いします。」と言われます。
最後に、上記のような裁判所からの指示を受けて、期日請書を裁判所に提出することになります。
期日請書を起案し、印刷して、押印をしたうえで、裁判所にFAXします。
期日請書についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.期日請書の根拠条文は、民事訴訟法94条2項但書です。
期日の呼び出しを受けた旨を記載した書面を提出した場合には、電話による期日指定でも、期日付遵守の不利益を負うことになります。
ただし、期日請書の提出を義務付ける根拠条文はないです。
A.期日請書の提出を求められてから、1週間程度しても期日請書が提出されていないと裁判所から催促の電話があります。
弁護士があえて期日請書を提出しないという場合には、呼出状の送達などが検討されることになります。
期日請書の提出義務はありませんが、結局、呼出状を送達されることになりますし、期日は遵守すべきものなので、提出に協力した方がいいでしょう。
A.問題ありません。
期日請書はfaxで提出するのが通常です。
効率的に期日を指定するために電話で期日を伝えているため、郵送よりもfaxで迅速に送った方が望ましいでしょう
A.送付状をつけてもいいですが、つけなくても問題ありません。
相手方当事者に直送するような書面ではなく受領書の返送なども想定されていませんし、1枚の書面となることが多いのであえて送付状を付けるメリットも乏しいためです。
ただし、誤faxをした場合を想定するなら、送付状を添付して「機密性の高い文書であること。心当たりない場合には破棄いただきたい。」ことを添えておくと丁寧です。
A.期日請書には、弁護士名の横に押印をして送付するのが通常です。


弁護士コンパスで
各分野に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、期日請書とは何かを説明したうえで、実務書式やひな形と簡単な書き方を弁護士が解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・期日請書とは、裁判所から期日の呼び出しを受けた際に提出する指定された期日を了承する書面のことです。
・期日請書には、「頭書事件につき、第1回期日を令和●年●月●日午後●時●分との指定を受けましたので、お請けいたします。」などの記載をします。
・期日請書の提出が求められるケースとしては、以下の3つがあります。
ケース1:原告・申立人側で第1回期日が指定された場合
ケース2:期日が変更された場合
ケース3:期日外で期日が指定された場合
・期日請書を提出する流れは、以下のとおりです。
流れ1:書記官から期日が決まったとの連絡が来る
流れ2:期日請書の提出を求められる
流れ3:期日請書を提出する
この記事が期日請書について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する

小藤貴幸
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階
詳細はこちら

三部達也
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階
詳細はこちら
-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)
髙田晃央
髙田法律事務所
東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504
詳細はこちら

籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら

鴨下香苗
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階
詳細はこちら

杉本拓也
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
詳細はこちら

内田拓志
https://uchida-takushi-law.com/
東京都千代田区一番町19番地
詳細はこちら

加藤惇
東日本総合法律会計事務所
東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階
詳細はこちら
人気記事

2025年5月2日
法律一般
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日
法律手続
裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日
法律手続
債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。